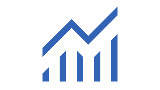せっかくお客様がホームページを訪問してくれたのに、すぐに他のサイトに移ってしまう。そんな悩みを抱えている中小企業や商店の経営者の方は多いのではないでしょうか。
ホームページの離脱率とは、訪問者があなたのサイトを見た後、他のサイトに移動してしまう割合のことです。例えば、100人がサイトを訪問して70人が他のサイトに移動した場合、離脱率は70%となります。
多くの中小企業で離脱率の高さが課題となっていますが、重要なのは、適切な改善策を実施することで、この数値を大幅に下げることができるという点です。
離脱率が10%改善されるだけで、月間1000人の訪問者がいる場合、100人多くの方にサービスや商品を詳しく見てもらえることになります。これは売上に直結する重要な改善ポイントなのです。
離脱率が高くなる5つの原因
ページの読み込み速度が
遅い
現代のお客様は待つことに慣れていません。ページの表示に3秒以上かかると、約40%の人が他のサイトに移動してしまいます。特にスマートフォンでの閲覧時は、この傾向がさらに顕著になります。
重い画像ファイルや複雑なデザインが原因で、ページの読み込みが遅くなっているケースが多く見られます。お客様がイライラしてサイトを離れてしまう前に、速度改善を行うことが重要です。
スマホ対応
ができていない
現在、ホームページの訪問者の約70%がスマートフォンからアクセスしています。しかし、多くの中小企業のサイトは、まだパソコン表示を前提とした作りになっており、スマホで見ると文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりします。
スマホで快適に閲覧できないサイトは、お客様にとって使いにくく、すぐに離脱の原因となってしまいます。
求める情報が
すぐに見つからない
お客様がサイトを訪問する理由は明確です。営業時間を知りたい、料金を確認したい、場所を調べたい、予約をしたいなど、具体的な目的を持っています。
しかし、これらの情報がトップページから簡単に見つけられない場合、お客様は諦めて他のサイトに移動してしまいます。必要な情報へのアクセスのしやすさが、離脱率に大きく影響します。
信頼性に欠ける
要素がある
古い情報が放置されていたり、連絡先が不明確だったりすると、お客様は「このお店は本当に営業しているのか」「信頼できるのか」と不安になります。
特に初めて訪問するお客様にとって、サイトの第一印象は非常に重要です。信頼性に疑問を感じた瞬間に離脱してしまうケースが多々あります。
次のアクション
が不明確
お客様がサイトを見て興味を持った後、「次に何をすればいいのか」が分からない状況は致命的です。電話をかけるべきなのか、予約フォームを使うべきなのか、来店すればいいのか。
明確な行動指針がないと、お客様は迷ってしまい、結果的にサイトを離れてしまいます。
【業種別】離脱率改善の成功事例
美容院A店:予約率30%アップの改善事例

この美容院では、改善前に深刻な問題を抱えていました。料金表がメニューページの奥に隠れており、お客様が価格を確認するまでに何度もクリックする必要がありました。また、予約方法が電話のみで、営業時間外は予約できない状況でした。さらに、スタッフ紹介がなく、どんな人に担当してもらえるか分からないため、初回来店への不安を抱えるお客様が多くいました。
改善策として、まずトップページに主要メニューと価格を大きく表示しました。お客様が最初に見るページで、すぐに料金を確認できるようになったのです。次に、24時間対応のオンライン予約システムを導入し、深夜や早朝でも予約が可能になりました。さらに、スタッフの顔写真と得意分野を紹介するページを作成し、お客様が安心して予約できる環境を整えました。
結果として、月間予約数が30%増加し、特に新規顧客の予約が大幅に向上しました。お客様からは「安心して予約できる」という声が多く寄せられ、リピート率も向上しています。
飲食店B店:問い合わせ2倍増の改善事例
この飲食店の課題は、古くなったメニュー写真でした。実際の料理よりも見劣りする写真が掲載されており、お客様の食欲をそそることができていませんでした。また、席数や個室の有無が分からず、団体客が予約を躊躇する状況でした。アクセス情報も分かりにくく、初回来店のハードルが高い状態でした。
改善に向けて、プロカメラマンによる料理写真の撮り直しを実施しました。湯気の立つ温かい料理や、色鮮やかな食材を使った写真により、サイトを見ただけで食べたくなるような魅力的な表現ができるようになりました。店内の雰囲気が分かる写真も多数掲載し、お客様が来店前にお店の雰囲気を把握できるようにしました。さらに、Googleマップを埋め込み、最寄り駅からの道順を詳しく説明することで、初回来店の不安を解消しました。
この改善により、月間問い合わせ件数が2倍に増加し、特に宴会予約が大幅に向上しました。来店率も20%アップし、売上向上に直結する成果を得ることができました。

小売店C店:オンライン売上50%向上の改善事例

この小売店では、商品の詳細情報が不足していることが大きな問題でした。サイズや材質、使用方法などの基本情報が欠けており、お客様が購入を判断する材料が不十分でした。在庫状況も分からず、せっかく購入を決意したお客様が在庫切れを理由に購入を諦めるケースが頻発していました。配送料や返品条件も不明確で、お客様に不安を与えていました。
改善策として、商品ページに詳細なスペック表と実際の使用例を追加しました。お客様が商品を手に取って確認できない分、文字と写真で十分な情報を提供することに注力しました。リアルタイム在庫表示システムを導入し、お客様がその場で在庫状況を確認できるようになりました。送料や返品ポリシーも分かりやすく表示し、購入前の不安を解消しました。
これらの改善により、オンライン売上が50%向上し、カート放棄率も大幅に改善しました。顧客満足度調査でも「安心して購入できる」という評価が向上し、リピート購入率も上昇しています。
今すぐできる離脱率改善10の対策
無料
スマホ表示の最適化チェック

まずは自分のスマートフォンで自社サイトを確認してみましょう。文字は読みやすいサイズになっているか、ボタンは指で押しやすい大きさになっているかをチェックします。
特に重要なのは、電話番号がタップできるリンクになっているかどうかです。お客様がスマホで電話番号を見つけた時、その番号をタップするだけで電話をかけられる状態になっていることが理想です。メニューが見やすく表示されているか、写真が適切なサイズで表示されているかも確認しましょう。
家族や友人にも協力してもらい、異なる機種での表示確認を行うことをお勧めします。機種によって表示が大きく異なる場合があるため、複数の端末で確認することが重要です。
無料
電話番号・営業時間の見やすさ改善

お客様が最も求める情報の一つが連絡先と営業時間です。これらの情報は、サイトのどのページからでも3秒以内に確認できる場所に配置する必要があります。
理想的な配置場所は、ヘッダー部分(サイトの上部)やサイドバー、フッター部分です。特にスマートフォンでは、画面下部に固定表示される「電話をかける」ボタンを設置することで、離脱率を大幅に改善できます。営業時間については、曜日別の詳細な時間だけでなく、祝日の営業状況や臨時休業の予定なども含めて表示することが重要です。
無料
写真・画像の最適化

古い写真や解像度の低い画像は、お客様に良くない印象を与えます。スマートフォンでも十分にきれいに撮影できる現在、プロに依頼しなくても魅力的な写真を用意することは可能です。
商品写真、店内写真、スタッフ写真など、お客様が興味を持ちそうな画像を定期的に更新しましょう。撮影時は、自然光を活用し、商品や店舗の魅力が最大限に伝わるアングルを選ぶことが重要です。ただし、ファイルサイズが大きすぎるとページの読み込み速度が遅くなるため、適切なサイズに圧縮することも忘れてはいけません。
無料
トップページの情報整理

トップページは、お客様が最初に目にする重要なページです。ここで必要な情報がすぐに見つからないと、他のページを見ることなく離脱してしまいます。
優先的に表示すべき情報は、事業内容の概要、主要なサービス・商品、連絡先、営業時間、アクセス情報です。これらを整理して、視覚的に分かりやすく配置しましょう。情報の優先順位を明確にし、最も重要な情報を画面の上部に配置することで、お客様の利便性が大幅に向上します。
無料
問い合わせ方法の明確化

お客様が興味を持った時に、すぐに連絡が取れる環境を整えることが重要です。電話、メール、問い合わせフォーム、SNSなど、複数の連絡手段を用意し、それぞれの特徴を明記しましょう。
例えば「お急ぎの方は電話、詳しい相談はメール、簡単な質問はLINE」といった具合に、用途別に案内することで、お客様の利便性が向上します。それぞれの連絡手段に対する対応時間も明記することで、お客様の期待値を適切に設定できます。
中級
ページ読み込み速度の改善

ページの読み込み速度は、離脱率に直結する重要な要素です。Googleの「PageSpeed Insights」という無料ツールを使用して、自社サイトの速度を測定してみましょう。
改善方法としては、画像ファイルの圧縮、不要なプラグインの削除、キャッシュ機能の活用などがあります。画像圧縮は、画質を大きく損なうことなくファイルサイズを50-70%程度削減できる場合が多く、即座に効果を実感できる改善策です。これらの作業は、基本的な知識があれば自分で実施することも可能です。
中級
お客様の声・レビューの掲載

実際にサービスを利用したお客様の声は、新規顧客の不安を解消する強力なツールです。写真付きの体験談や、具体的な効果を記載したレビューを掲載することで、サイトの信頼性が大幅に向上します。
お客様にレビューの協力をお願いする際は、具体的な質問を用意することが効果的です。「どんな点が良かったですか?」「他の人にお勧めしたいポイントは?」「利用前と後で何が変わりましたか?」といった質問により、より詳細で説得力のある内容を集めることができます。
中級
よくある質問(FAQ)ページの充実

お客様からよく受ける質問をまとめたFAQページは、離脱率改善に非常に効果的です。お客様の疑問を事前に解決することで、安心してサービスを利用してもらえます。
FAQには、料金体系、サービス内容、予約方法、キャンセルポリシーなど、お客様が気になる点を網羅的に掲載しましょう。単純な質問と答えの羅列ではなく、お客様の立場に立った丁寧な説明を心がけることが重要です。定期的に内容を見直し、新しい質問があれば随時追加することも忘れてはいけません。
有料
オンライン予約・問い合わせシステムの導入

24時間いつでも予約や問い合わせができるシステムは、機会損失を防ぐ重要なツールです。特に営業時間外にサイトを訪問するお客様にとって、その場で予約できることは大きなメリットとなります。
最近では、月額数千円から利用できる予約システムも多数提供されており、中小企業でも導入しやすくなっています。システム選択の際は、操作の簡単さとお客様にとっての使いやすさを重視しましょう。複雑すぎるシステムは、かえって離脱率を高める原因となってしまいます。
有料
プロによる写真撮影

魅力的な写真は、お客様の興味を引く最も効果的な方法の一つです。商品写真、店舗写真、スタッフ写真など、プロカメラマンによる撮影を検討してみましょう。
投資額は数万円程度ですが、その効果は長期間にわたって持続します。特に飲食店や美容院など、視覚的な魅力が重要な業種では、写真の品質向上による効果は非常に高くなります。プロの撮影では、照明や構図の技術により、商品やサービスの魅力を最大限に引き出すことができます。
離脱率改善のチェックリスト
定期的にサイトの状況を確認するために、以下のポイントをチェックしてみましょう。
基本情報の確認について: 営業時間が最新の情報に更新されているか、電話番号がスマホでタップできるようになっているか、住所とアクセス方法が分かりやすく記載されているか、主要なサービス・商品がトップページで確認できるかを定期的に確認することが重要です。
スマートフォン対応について: 文字が読みやすいサイズになっているか、ボタンが指で押しやすい大きさになっているか、横スクロールが発生していないか、メニューが使いやすく設計されているかをチェックしましょう。
コンテンツの質について: 写真が鮮明で魅力的に表示されているか、情報が最新の内容に更新されているか、お客様の声やレビューが掲載されているか、よくある質問が充実しているかを確認します。
ユーザビリティについて: ページの読み込み速度が適切である(3秒以内)か、必要な情報にすぐにアクセスできるか、問い合わせ方法が明確に示されているか、次に取るべき行動が分かりやすいかを検証することが大切です。
よくある質問(FAQ)
離脱率と直帰率の違いについて
離脱率と直帰率は似ているようで異なる指標です。直帰率は「1ページだけ見てサイトを離れる割合」を示し、離脱率は「そのページを最後にサイトを離れる割合」を示します。直帰率はサイト全体の魅力度を測る指標として、離脱率は各ページの完成度を測る指標として活用できます。
改善効果が現れる時期について
改善効果の現れ方は、実施する対策によって大きく異なります。基本的な改善である連絡先の明記や写真の更新などは、実施後すぐに効果が現れることが多いです。一方、SEO対策や本格的なサイトリニューアルの効果は、検索エンジンの評価が変わるまでに時間がかかるため、2-3ヶ月程度で効果が現れることが一般的です。
予算をかけない改善策について
多くの改善策は、実は無料で実施することが可能です。スマートフォンでの表示確認、基本情報の整理、自分で撮影した写真への更新など、工夫次第で大きな改善効果を得ることができます。重要なのは、お客様の立場に立ってサイトを見直すことです。
最初に取り組むべき改善策について
改善に取り組む際は、まず基本情報の見直しから始めることをお勧めします。営業時間、連絡先、アクセス方法などの基本情報は、費用をかけずに即座に改善でき、効果も高いためです。これらの情報が正確で見つけやすい状態になってから、より高度な改善策に取り組むことが効率的です。
改善効果の測定方法について
改善効果を測定するためには、月間の問い合わせ件数、予約件数、来店客数などの変化を記録することが重要です。改善前の数値を基準として、改善後の変化を追跡することで、どの施策が効果的だったかを把握できます。数値の記録は簡単なメモでも十分ですが、継続的に記録することが成功の鍵となります。
まとめ
ホームページの離脱率改善は、中小企業や商店にとって売上向上に直結する重要な取り組みです。高度な技術や多額の予算は必要ありません。お客様の立場に立って、使いやすく信頼できるサイトを作ることが最も重要です。
今回ご紹介した改善策を参考に、できることから少しずつ実践していけば、必ず効果を実感していただけるはずです。お客様にとって価値のあるサイトを作ることで、ビジネスの成長につなげていきましょう。