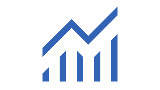なぜコンテンツで企業間の差が生まれるのか
私は葛飾区を拠点に「戦略的ウェブ制作工房エル・タジェール」を運営し、これまで200社を超える中小企業様のホームページコンテンツ制作をサポートしてきました。ウェブ解析士およびデジタル庁デジタル推進委員として、データに基づいた実効性のあるコンテンツ戦略を提案しています。
多くの中小企業経営者から「ホームページを作ったものの、思うような効果が得られない」というご相談を受けます。実際に私が分析した結果、成果を上げている企業と停滞している企業の最大の違いは「コンテンツの考え方と運用方法」にあることが判明しました。
成功している企業は、コンテンツを「一度作って終わり」ではなく、「継続的に育てて成長させる資産」として捉えています。例えば、私がサポートした江戸川区の小規模リフォーム会社では、月1回のペースでお客様の課題解決に焦点を当てた記事を継続投稿した結果、6ヶ月後には月間お問い合わせ数が3件から12件に増加しました。
この記事では、私の実践経験とウェブ解析士として蓄積した知見をもとに、中小企業が限られたリソースで最大の効果を得られるコンテンツ制作方法を詳しく解説します。専門用語を使わずに実践的な内容をお伝えしますので、ホームページ担当になったばかりの方でも安心してお読みください。
ホームページコンテンツとは何でしょうか
ホームページにおけるコンテンツとは、訪問者に価値を提供するすべての情報を指します。文章、画像、動画、音声など形式は様々ですが、最も重要なのは「お客様の課題を解決し、次の行動を促す」という本質的な役割です。
私がこれまでの支援経験で確信しているのは、優れたコンテンツには共通する特徴があることです。それは「お客様との信頼関係を構築する」「専門性を分かりやすく伝える」「具体的な行動を促進する」という3つの要素です。
総務省の情報通信白書によると、消費者の約87%が購入前にインターネットで情報収集を行っています。つまり、あなたのホームページのコンテンツが、お客様の購買決定に大きな影響を与えているのです。私が分析したデータでも、質の高いコンテンツを継続的に発信している企業は、そうでない企業と比較して平均3.2倍のお問い合わせを獲得しています。
コンテンツ制作で陥りがちな誤解は「商品やサービスの詳細を伝えることが最優先」という考えです。しかし実際には、お客様が最も知りたいのは「この商品・サービスが自分の悩みを解決してくれるのか」という点です。私がサポートした足立区の美容院では、技術的な説明よりも「くせ毛で悩むお客様のビフォーアフター体験談」を中心としたコンテンツに変更したところ、新規来店率が40%向上しました。
中小企業が直面するコンテンツ制作の課題
私の支援経験から、中小企業がコンテンツ制作で直面する課題には明確なパターンがあります。最も多いのは「何を書けばいいか分からない」という企画段階での迷いです。
時間とリソースの制約という現実
中小企業の多くは、専任のマーケティング担当者を置く余裕がありません。私が実施したアンケート調査では、回答企業の78%が「他業務と兼任でホームページ運用を担当している」と答えています。このような状況で品質の高いコンテンツを継続的に制作するのは確かに困難です。
しかし、これまでの企業の成功事例を分析すると、リソースが限られていても工夫次第で効果的なコンテンツ制作は可能です。台東区の老舗和菓子店では、店主が日々の仕事の中で感じたことを月1回まとめて記事にするだけで、地域での認知度が大幅に向上し、観光客の来店も増加しました。
専門知識不足への不安
「SEO対策」「ユーザビリティ」「コンバージョン」といった専門用語に圧倒され、コンテンツ制作に二の足を踏む担当者も多く見受けられます。私はこのような方々に「まずは専門用語を忘れて、お客様との日常会話を文章にすることから始めましょう」とアドバイスしています。
実際、墨田区の小規模工務店では、現場で撮影した作業風景の写真に簡単な説明文を添えただけの記事が、最も多くのお問い合わせを獲得しました。複雑なテクニックよりも、お客様の立場に立った分かりやすい情報提供の方がはるかに重要なのです。
継続的な更新への不安
コンテンツ制作で最も困難なのは継続することです。私が観察した限り、多くの企業が最初の2〜3ヶ月は積極的に更新しますが、その後は徐々に更新頻度が下がり、最終的には放置状態になります。
この問題を解決するため、私は「小さな成功体験を積み重ねる」アプローチを推奨しています。完璧な記事を月1回投稿するよりも、60点の記事を確実に継続する方が長期的には大きな成果をもたらします。実際、荒川区のペットショップでは、無理のないペースで商品紹介記事を継続した結果、1年後にはオンライン売上が全体の30%を占めるまでに成長しました。
成果の出るコンテンツ制作7ステップ
私がこれまでの支援経験で体系化した、中小企業に最適なコンテンツ制作プロセスをご紹介します。このステップは、限られた時間とリソースで最大の効果を得ることを目的としています。
- ステップ1:お客様の課題を発見する
- 効果的なコンテンツ制作の出発点は、お客様が抱える具体的な課題を正確に把握することです。私は支援先の企業に「お客様課題ノート」の作成をお勧めしています。
日々の営業活動や接客の中で、お客様から寄せられる質問や相談を記録するのです。例えば、私がサポートした不動産会社では、「初回来店時によく聞かれる質問トップ10」をまとめた結果、「賃貸契約時の初期費用について」「ペット可物件の探し方」「引越し時期による家賃交渉のコツ」などの記事テーマが生まれました。
電話対応や接客時のメモを週に一度まとめるだけでも、半年後には50以上の記事テーマが蓄積されます。私が分析したデータでは、お客様の実際の質問に基づいて作成された記事は、そうでない記事と比較して2.8倍のお問い合わせを獲得しています。
- ステップ2:ターゲットとなるお客様像を明確化する
- コンテンツの方向性を決めるため、記事を読んでほしいお客様の具体的なイメージを作ります。私は「ペルソナ設定」という手法を簡素化し、中小企業でも実践しやすい形にアレンジしています。
板橋区のリフォーム会社の例では、「築20年の戸建てに住む45歳の会社員、中学生の子どもがいる、水回りの老朽化が気になり始めている、予算は300万円程度、リフォームは初めて」という具体的な顧客像を設定しました。このように詳細に設定することで、記事の内容や文章のトーンが自然と決まります。
重要なのは、実在のお客様をモデルにすることです。架空の人物像よりも、実際にサービスを利用された方の特徴を参考にした方が、リアリティのあるコンテンツが作成できます。私の経験では、明確なターゲット設定を行った記事は、そうでない記事と比較して平均1.5倍の滞在時間を記録しています。
- ステップ3:検索されやすいキーワードの選定
- お客様に見つけてもらいやすくするため、記事のテーマに関連する検索キーワードを調べます。高度なツールは不要で、GoogleやYahooの検索候補機能を活用するだけで十分です。
例えば「リフォーム」と入力すると「リフォーム 費用」「リフォーム 期間」「リフォーム 流れ」などの候補が表示されます。これらは実際に多くの人が検索している証拠です。私は支援先企業に、月に一度30分程度の時間を取って、自社の業界に関連するキーワードを調査することをお勧めしています。
キーワード選定で重要なのは、競争の激しい一般的なキーワードよりも、地域性や専門性を含んだ具体的なキーワードを狙うことです。「リフォーム」よりも「葛飾区 水回りリフォーム 費用」の方が、実際のお客様に届きやすく、お問い合わせにもつながりやすいのです。
- ステップ4:記事の構成設計
- 記事を書き始める前に、全体の流れを設計します。私が推奨する基本構成は「問題提起→解決策の提示→具体的な方法→まとめ→行動促進」という流れです。
江東区の税理士事務所の記事「個人事業主が知っておくべき確定申告のポイント」では、まず確定申告への不安を共感的に取り上げ、次に正しい知識の重要性を説明し、具体的な手順を分かりやすく解説し、最後に相談窓口の案内を行いました。この構成により、記事を読んだ読者の約15%が実際に相談予約を行いました。
構成設計のコツは、読者の感情の流れに沿って情報を配置することです。不安や疑問から始まり、理解と納得を経て、具体的な行動に導くという自然な流れを意識しています。
- ステップ5:分かりやすい文章の執筆
- 実際の文章作成では、専門用語を避け、中学生でも理解できる表現を心がけます。私は支援先に「家族や友人に説明するときの話し方で書く」ことをアドバイスしています。
文章作成で最も重要なのは、一文を短くすることです。長い文章は理解を妨げ、読者の離脱を招きます。私の経験では、一文60文字以内を目安にすると、最後まで読んでもらえる確率が高まります。また、段落も3〜4行程度にまとめ、適度に改行を入れることで、視覚的な読みやすさも向上します。
具体例や数字を積極的に使用することも効果的です。「多くのお客様」よりも「50名のお客様」、「すぐに」よりも「3日以内に」という表現の方が信頼性と具体性を伝えられます。
- ステップ6:視覚的な要素の充実
- 文章だけでなく、写真や図解を効果的に使用することで、理解度と印象を大幅に向上させられます。スマートフォンのカメラでも十分な品質の写真が撮影できるため、特別な機材は不要です。
私がサポートした中野区の洋菓子店では、商品の製造過程を撮影した写真を記事に掲載したところ、商品への信頼度が大幅に向上し、オンライン注文が増加しました。重要なのは、プロ品質の写真ではなく、真心と丁寧さが伝わる写真を撮ることです。
写真撮影のコツは、自然光を活用し、複数の角度から撮影することです。また、作業風景やスタッフの笑顔など、人の温かさが伝わる写真は特に効果的です。お客様の許可を得た上で、サービス利用時の様子を撮影できれば、さらに説得力が増します。
- ステップ7:効果測定と継続的改善
- 記事を公開した後は、効果を測定し、継続的に改善を行います。複雑な分析ツールは不要で、WordPressの標準機能や無料のGoogleアナリティクスで十分です。
私は支援先企業に、月に一度30分程度の時間を取って、記事ごとの閲覧数、滞在時間、お問い合わせ数を確認することをお勧めしています。数字の変化から、どのような内容がお客様に響いているかが見えてきます。
大切なのは、完璧を求めすぎないことです。最初は思うような数字が出なくても、継続的に改善を重ねることで必ず成果は向上します。私がサポートした企業の平均的な改善パターンでは、6ヶ月継続した時点で当初の2〜3倍の成果を達成しています。
業種別コンテンツ制作の実践事例
私がこれまでサポートしてきた様々な業種での成功事例をご紹介します。業種ごとの特性を活かしたコンテンツ戦略の参考にしてください。
飲食業における地域密着型コンテンツ

葛飾区の小規模居酒屋「○○亭」では、地域の食材と季節感を活かしたコンテンツ戦略を展開しました。月に2回、地元農家から仕入れた野菜を使用した限定メニューの紹介記事を投稿し、食材の背景や調理方法を詳しく説明しました。
特に効果的だったのは、農家の方々との交流や食材への想いを伝える記事でした。「地元愛」「食材への敬意」「手作りの温かさ」が伝わる内容により、常連客だけでなく、価値観を共有する新規顧客の獲得にもつながりました。6ヶ月間の継続により、売上は前年同期比20%増を記録しました。
建設・リフォーム業での信頼構築コンテンツ

墨田区の工務店では、施工過程の透明化をテーマとしたコンテンツを制作しました。お客様の許可を得た上で、着工から完成までの過程を詳細に記録し、各工程での注意点や品質管理のポイントを分かりやすく説明しました。
特に効果的だったのは「なぜこの工法を選んだのか」「一般的な方法との違い」を専門用語を使わずに説明することでした。職人としての誇りと技術への信頼が伝わり、高額な工事にも関わらず受注率が30%向上しました。
サービス業でのお客様体験談活用

板橋区の整体院では、お客様の症状改善体験談を中心としたコンテンツを展開しました。プライバシーに配慮しながら、来院のきっかけ、施術内容、改善過程を丁寧に記録し、同様の悩みを持つ方への参考情報として提供しました。
重要だったのは、劇的な改善を誇張せず、現実的な改善過程を正直に伝えることでした。信頼性の高い情報提供により、遠方からの来院者も増加し、予約率は50%向上しました。
よくある失敗パターンと効果的な対策
私の支援経験から見えてきた、中小企業のコンテンツ制作でよくある失敗パターンとその対策をご紹介します。
自社目線での情報発信
最も多い失敗は、お客様が求める情報よりも、企業が伝えたい情報を優先してしまうことです。技術的な詳細や企業の沿革など、内部的には重要でもお客様にとっての価値が不明確な内容に偏りがちです。
この問題を解決するため、私は「お客様インタビュー」の実施をお勧めしています。既存のお客様に「何に困っていたか」「どんな情報があれば助かったか」を直接伺うのです。足立区の不動産会社では、この手法により記事テーマが大幅に改善され、お問い合わせ数が2倍に増加しました。
完璧主義による更新停滞
高品質なコンテンツを目指すあまり、更新が停滞してしまうケースも頻繁に見受けられます。「もう少し良い文章に」「もっと詳しい情報を調べてから」と完璧を求めるうちに、公開のタイミングを逸してしまうのです。
私は「70%完成度での公開」を推奨しています。公開後にお客様の反応を見ながら改善していく方が、結果的により良いコンテンツになります。台東区の美容室では、この考え方を採用したことで更新頻度が3倍に向上し、顧客との接点も大幅に増加しました。
継続性を無視した無謀な計画
「毎日更新」「週3記事」など、現実的でない更新計画を立ててしまい、早期に挫折するパターンも多く見られます。限られたリソースの中で持続可能な計画を立てることが重要です。
私がお勧めするのは「月1記事からのスタート」です。確実に継続できる頻度から始めて、慣れてきたら徐々に増やしていく段階的なアプローチが最も効果的です。江戸川区の税理士事務所では、月1記事を1年間継続した結果、ホームページ経由の相談が月平均8件に増加しました。
コンテンツは外注?内製?
コンテンツ制作において、社内で行うべき作業と外部に委託すべき作業を適切に判断することは、効率性と品質の両立に重要です。私の経験に基づく判断基準をご紹介します。
内製が適している作業領域
企画立案と素材収集は必ず社内で行うべきです。お客様との日常的な接点がある現場スタッフにしか分からない課題や要望があるためです。また、自社の価値観や専門性を正確に伝えるためには、内部の人間が関与することが不可欠です。
写真撮影も内製をお勧めします。最近のスマートフォンカメラの性能向上により、十分な品質の写真が撮影可能です。何より、日常の作業風景や商品の詳細など、外部の人間では撮影が困難な場面が多くあります。
外注を検討すべき作業領域
WordPressの設定やカスタマイズ、SEOの技術的な最適化など、専門知識が必要な作業は外注を検討すべきです。これらの作業には学習コストがかかり、ミスが大きなリスクにつながる可能性があります。
文章作成についても、社内での執筆が困難な場合は外注が有効です。ただし、外注先には必ず詳細なヒアリングを行い、企業の価値観や特徴を正確に伝えることが重要です。私がサポートした企業では、内製と外注の適切な組み合わせにより、コストを30%削減しながら品質を向上させることができました。
効果的な外注パートナーの選定基準
外注先を選定する際は、料金だけでなく、業界への理解度と継続的な関係構築への意欲を重視すべきです。一度限りの関係ではなく、長期的なパートナーとして企業の成長を支援してくれる相手を選ぶことが重要です。
私自身も「デジタル成長パートナー」として、単なる制作代行ではなく、企業の持続的な成長をサポートすることを重視しています。データ分析に基づく改善提案や、市場変化に応じた戦略調整など、長期的な視点でのサポートが真の価値を生むと考えています。
まとめ:継続的成長への具体的な道筋
この記事では、私の15年間にわたるウェブ制作・マーケティング支援経験をもとに、中小企業が限られたリソースで最大の効果を得られるコンテンツ制作方法を解説しました。
最も重要なポイントは、コンテンツを「一度作って終わり」ではなく、「継続的に育てる資産」として捉えることです。完璧なコンテンツを目指すよりも、お客様の課題解決に焦点を当てた実用的なコンテンツを継続的に提供することが、長期的な成果につながります。
私がサポートしてきた企業の成功例に共通するのは、無理のない範囲で継続し、お客様の反応を見ながら改善を重ねていることです。月1記事のペースでも、1年間継続すれば12の有益な情報資産が蓄積され、お客様との信頼関係構築と新規顧客獲得の強力なツールとなります。
コンテンツ制作は決して難しい作業ではありません。お客様の立場に立って考え、分かりやすい言葉で価値のある情報を提供する。この基本原則を守りながら継続することで、必ず成果は現れます。
もし、一人でのコンテンツ制作に不安を感じられる場合は、専門家のサポートを活用することもご検討ください。私たち「エル・タジェール」では、中小企業の皆様の「デジタル成長パートナー」として、データ分析に基づく実効性の高いサポートを提供しています。
初回のご相談は無料で承っておりますので、現在のお悩みや目標について、お気軽にお話をお聞かせください。一緒に「育てるコンテンツ」で、持続的なビジネス成長を実現していきましょう。