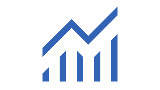こんにちは。戦略的ウェブ制作工房エル・タジェールの宮崎です。
私は東京都葛飾区でWordPress専門として、町の工務店から製造業、美容院、士業事務所まで、これまで多くの中小企業様のホームページ制作・改善をお手伝いしてきました。
その中でよく聞かれるのが「文章がうまく書けない」「何を書けばいいか分からない」というお悩みです。でも安心してください。実は文章には「型」があり、それさえ覚えれば誰でも読みやすい文章が書けるようになります。
実際、昨年支援した町の不動産屋さんでは、お客様によく聞かれる「住宅ローンの流れ」を分かりやすく書いただけで、相談の電話が月2-3本から月8-10本に増えました。町の税理士事務所では、難しい税務の話を「中学生でも分かる言葉」で説明し直したところ、新規の相談が3倍に増えたという報告をいただいています。
この記事では、WordPress専門家として200サイト以上を手がけた経験から、中小企業や商店の担当者でも今すぐ実践できる「読みやすい文章の書き方」をお伝えします。難しいツールや専門知識は一切不要です。明日からすぐに使える実践的な方法だけをご紹介します。
なぜ中小企業のホームページは読まれないのか?
まず、なぜ多くの中小企業のホームページが「読まれない」のかを理解しましょう。これは決して文章力の問題ではありません。
「何を書けばいいか分からない」の正体
多くの担当者が「何を書けばいいか分からない」と悩まれますが、実はこれ、書く内容が思い浮かばないのではなく、「お客様が何を知りたがっているか」が見えていないだけなのです。
例えば、工務店の場合。「当社は創業50年の実績があります」「高品質な施工をお約束します」といった会社目線の内容ばかり書いてしまいがちです。でも、お客様が本当に知りたいのは「家を建てるのにいくらかかるの?」「工事期間はどのくらい?」「近所に迷惑をかけない?」といった具体的な疑問なんです。
競合と同じような内容になってしまう理由
業界の常識にとらわれすぎると、どこも似たような内容になってしまいます。美容院なら「カット、カラー、パーマ承ります」、税理士なら「確定申告、法人設立、相続相談」といった具合に。
でも考えてみてください。お客様がホームページを見るのは、サービス内容を確認するためだけではありません。「この店(会社)は自分に合うかな?」「安心して任せられるかな?」を判断したいのです。
専門用語を使いすぎてしまう問題
これは私自身も気をつけていることですが、その道のプロになると、つい専門用語を使ってしまいます。建築なら「在来工法」「ツーバイフォー」、税務なら「青色申告」「損金算入」といった言葉です。
でも、お客様にとってはチンプンカンプン。分からない言葉が出てきた瞬間、「自分には関係ない」と感じて、そのページを閉じてしまうのです。
実際、弊社でリニューアルした製造業のクライアントでは、技術的な説明を「中学生でも分かる言葉」に変えただけで、問い合わせの内容が具体的になり、成約率が向上しました。
WordPress専門家が教える!今すぐできる文章改善法
ここからは、具体的な改善方法をお伝えします。どれも特別な知識は不要で、今日からすぐに実践できる方法です。
見出しはお客さんの疑問をそのまま使う
まず最も効果的なのが、見出しの改善です。会社目線の見出しではなく、お客様が実際に抱く疑問をそのまま見出しにしてください。
例えば、工務店の場合
改善前(会社目線)
「当社の施工実績」
「品質へのこだわり」
「アフターサービス」
改善後(お客様目線)
「家を建てるのに実際いくらかかるの?」
「工事中、近所に迷惑をかけない?」
「完成後に不具合があったらどうしてくれる?」
お客様は自分の疑問への答えを探しています。疑問がそのまま見出しになっていれば、「あ、これは私が知りたかったことだ」と思って読み進めてくれます。
冒頭3秒で「自分のことだ」と思わせる
ホームページを訪れた人は、最初の3秒で「このページは自分に関係があるか」を判断します。この3秒で心を掴むために、冒頭で読み手の状況や悩みを具体的に表現しましょう。
改善前(一般的すぎる)
「お客様に満足いただけるサービスを提供します」
改善後(具体的で共感しやすい)
「『税理士って敷居が高そう』『相談料がいくらかかるか不安』そんな風に思っている小さな会社の社長さんはいませんか?」
後者の方が「まさに自分のことだ」と感じますよね。
地域キーワードで親近感をアップ
中小企業や商店の最大の強みは「地域密着」です。この強みを文章でも活かしましょう。
改善前
「多くのお客様にご利用いただいています」
改善後
「葛飾区の皆様に30年間愛され続けています。亀有駅から徒歩5分、お買い物帰りにお気軽にお立ち寄りください」
地域名や駅名、地元の人しか知らないスポット名を入れることで、「地元の店だ」という安心感が生まれます。
お客様の声で説得力を3倍にする
どんな立派な説明よりも、実際のお客様の声の方が説得力があります。ただし、ありがちな「満足しています」といった感想ではなく、具体的なエピソードを紹介しましょう。
改善前(抽象的)
「お客様に大変満足いただいています」
改善後(具体的)
「工事中、毎日現場をきれいに片付けてくださり、近所の方からも『きちんとした業者さんですね』と言われました。完成後も『困ったことがあればいつでも連絡してください』と名刺を置いていってくれて、とても安心です」(40代女性・新築一戸建て)
このように具体的なエピソードがあると、読んでいる人は「自分もこんな風に大切にしてもらえるんだな」と感じるのです。
写真は説明よりも雄弁
文章だけでは伝わりにくい部分は、写真で補いましょう。特に、作業の様子やスタッフの表情が分かる写真は効果的です。
例えば、清掃業なら作業前後の写真、美容院なら施術中の丁寧な様子、製造業なら実際に作業している職人さんの写真などです。
大切なのは「プロ感」よりも「人間味」です。少しぐらいぶれていても、スタッフの人柄が伝わる自然な写真の方が親しみやすく感じられます。
難しい言葉は中学生レベルに
専門用語はできるだけ使わず、中学生でも理解できる言葉に置き換えましょう。どうしても専門用語を使う必要がある場合は、必ず説明を添えてください。
改善前
「弊社では在来工法とツーバイフォー工法の両方に対応しています」
改善後
「木造住宅には大きく2つの建て方があります。日本で昔から使われている『在来工法(木の柱と梁で組む方法)』と、アメリカ生まれの『ツーバイフォー工法(壁で支える方法)』です。それぞれに良さがあるので、ご家族のご希望に合わせてご提案します」
このように説明があると、専門知識がない人でも安心して読み進められます。
段落は短く、余白をたっぷりと
文章がぎっしり詰まっていると、読む気が失せてしまいます。1つの段落は3〜4行程度に抑え、段落の間には余白を入れましょう。
スマートフォンで見ることも多いので、スマホの画面で確認して、適度に改行されているかチェックしてください。
WordPressでの実装のコツ
文章ができたら、次はWordPressでの見せ方です。技術的な部分もありますが、知っておくと効果的なポイントをお伝えします。
見出しタグの正しい使い方
WordPressで記事を書くとき、見出しには「見出し1」「見出し2」といった種類があります。これを正しく使うことで、読みやすさとSEO効果の両方が向上します。
記事のタイトルは「見出し1」、大きな章は「見出し2」、その中の小さな項目は「見出し3」というように、階層を意識して使いましょう。
読みやすくなるプラグイン
WordPressには、文章を読みやすくするプラグインがあります。私がよくお勧めするのは、目次を自動生成してくれるプラグインです。見出しから自動で目次を作ってくれるので、読み手が知りたい情報にすぐにたどり着けます。
また、文字の大きさや行間を調整できるプラグインもあります。特に年配のお客様が多い業種では、少し文字を大きめにするだけで読みやすさが大幅に向上します。
スマホでの見やすさをチェック
今は多くの人がスマートフォンでホームページを見ています。パソコンで見やすくても、スマホでは読みにくいということがよくあります。
記事を書いたら、必ずご自身のスマートフォンで確認してください。文字が小さすぎないか、写真が見やすいか、ボタンが押しやすいかなどをチェックしましょう。
効果を確認する簡単な方法
文章を改善したら、その効果を確認することが大切です。難しいツールは使わず、簡単な方法で効果を測定できます。
お問い合わせ数を記録する
最もシンプルで分かりやすいのが、お問い合わせ数の変化です。改善前と改善後で、月にどれくらいお問い合わせが来るかを記録しましょう。
エクセルやメモ帳でも構いません。「○月:電話3件、メール2件」といった具合に記録していけば、数ヶ月後に変化が見えてきます。
お客様の反応を記録する
お問い合わせや来店の際に、「ホームページのどの部分を見て連絡しましたか?」と聞いてみてください。「料金のページが分かりやすかった」「施工事例の写真を見て安心した」といった反応があれば、その部分は成功していることが分かります。
3ヶ月後の効果判定
文章の改善効果は、だいたい3ヶ月で見えてきます。以下の点をチェックしてみてください。
お問い合わせが増えたか、お問い合わせの内容がより具体的になったか、来店・来社されるお客様が「ホームページを見て」と言ってくれるかなどです。
数字で劇的な変化がなくても、お客様の反応が良くなっていれば改善は成功しています。
忙しい中でも続けられる更新のコツ
「継続は力なり」とは言いますが、忙しい中で定期的に更新するのは大変です。無理のない範囲で続けられる方法をお伝えします。
月1回30分だけの更新スケジュール
毎日更新する必要はありません。月に1回、30分だけ時間を作って、1つの記事を追加または更新しましょう。
例えば、毎月第2火曜日の午後3時からの30分を「ホームページ更新タイム」として決めておくのです。習慣化してしまえば、それほど負担に感じなくなります。
ネタ切れしないアイデア帳の作り方
「何を書けばいいか分からない」を防ぐために、普段からネタをメモしておきましょう。
お客様からよく聞かれる質問、季節ごとの注意点、業界の新しい動き、スタッフの何気ない一言など、日常の中にネタはたくさんあります。スマートフォンのメモ機能を使って、思いついたときにすぐ記録する習慣をつけましょう。
外注を検討するタイミング
もし売上が順調に伸びて、文章作成に時間をかけられなくなったら、外注を検討する時期かもしれません。
ただし、外注する場合も、お客様の声や具体的なエピソードは自社で集める必要があります。外部の人には分からない、現場の生の情報こそが、読み手の心を動かすからです。
まとめ:小さな改善が大きな成果を生む
ここまで、中小企業や商店のホームページ担当者でも今すぐ実践できる文章改善法をお伝えしました。
大切なのは、完璧な文章を書こうとすることではありません。お客様の立場に立って、お客様が知りたいことを、分かりやすい言葉で伝えることです。
見出しをお客様の疑問に変える、冒頭で共感を得る、地域性を活かす、お客様の声を活用する、写真で補完する、難しい言葉を避ける、適度に改行するといった小さな改善の積み重ねが、大きな成果を生みます。
私がこれまで支援してきた中小企業の多くが、こうした地道な改善によって「お問い合わせが増えた」「来店客が増えた」「成約率が上がった」という成果を実感されています。
文章は一朝一夕で上達するものではありませんが、お客様のことを思って書き続けていれば、必ず成果につながります。
もし改善後3ヶ月経っても効果が感じられない場合は、お気軽にご相談ください。WordPress専門家として、現場を知る者として、皆様の成功を心から応援しています。
ぜひ今日から、できることから始めてみてください。きっと3ヶ月後には、嬉しい変化を実感していただけるはずです。