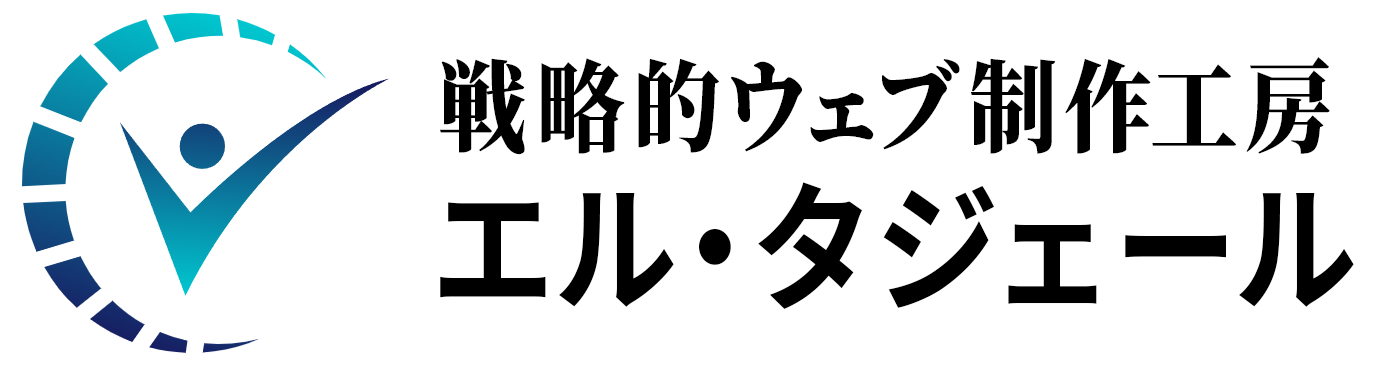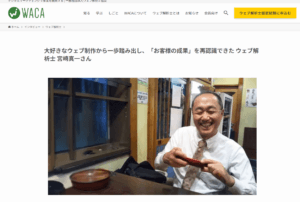人間にしかできない「想像する力」とは? 〜AI時代を生きる私たちへ〜
こんにちは。
近年、生成AIの進化が目覚ましく、文章、イラスト、音楽、さらにはプログラムの作成まで、かつて人間だけが担っていた創造的な作業の多くを、AIが代行できるようになってきました。
では、そんな時代において「人間にしかできないこと」とは何でしょうか?
私は、「想像すること」こそが、人間にしかできない力だと考えています。
想像とは何か?創造・共感・価値判断の源
「想像力」という言葉は、クリエイティブな才能を語るときによく使われますが、それだけではありません。
想像とは、「まだ存在しないものを思い描く力」であり、
それは創造(creative)の源泉であると同時に、
他者に共感し、善悪や価値を判断するための土台でもあります。
生成AIはデータをもとに無数のパターンを再構成することはできますが、
「なぜ、これを創るのか?」「それは誰に、どんな意味をもたらすのか?」といった**“問い”や“意図”**は、人間の想像力にこそ宿るものです。
教育の観点から:想像力を育てるには?
では、この想像力をどう育てていけるのでしょうか?
まずは教育の視点から見てみましょう。
◆ 正解のない問いに向き合う経験
詰め込み式の教育では、想像する余地が失われがちです。
「これが正解」ではなく、「あなたはどう思う?」と問われる機会こそ、想像を促します。
◆ 芸術や物語への触れ合い
音楽や文学、美術など、感性を刺激する体験は、自分の枠を越えて想像を広げてくれます。
多様な物語と出会うことは、他者の視点に立つきっかけにもなります。
◆ 異文化・多様性との接触
背景の異なる人々と触れ合うことは、自分の常識を相対化し、より豊かな想像力につながります。
生活の観点から:日常の中にある想像の種
日々の暮らしの中にも、想像力を育てるヒントはたくさんあります。
◆ “余白”のある時間
常にスマホや予定で埋まった毎日では、想像の余地は生まれません。
退屈な時間や、ふと立ち止まる散歩の途中にこそ、心の中に新しい風が吹き込むことがあります。
◆ 五感を使う暮らし
自然の匂い、季節の味、手の感触。五感を使って世界を感じることが、想像の土壌になります。
料理やものづくり、ガーデニングなども良い例ですね。
◆ 「なぜ?」を忘れない
日常の中に問いを持つこと――たとえば「なぜこの人はこう言ったのか?」「これって本当に必要?」と考えることが、想像の筋肉を鍛えてくれます。
想像を支える習慣と仕組み:エル・タジェールの取り組み
私たちエル・タジェールでは、「想像すること」は未来をつくる力であると信じています。
そのために、日々の業務の中にも、余白と“刺激を意識的に取り入れています。
たとえば、私たちは全体の作業時間の20%を、学習やクリエイティブ活動にあてることをルールとしています。これは、日々の業務の効率や技術向上だけでなく、「想像の力を育て続ける」ための時間です。

また、チケットサブスクサービス「recri(レクリ)」を利用して、毎月美術展や企画展に足を運ぶようにしています。日常から少し離れた場所でアートや表現に触れることで、発想の幅が広がり、自分の価値観に新しい視点を加えるきっかけになっています。
想像は「未来をつくる力」
私たちはこれから、AIと共に生きていく時代を迎えます。
AIは確かに強力なツールですが、それをどう使うか、何のために使うか――
その問いを立てるのは、やはり人間です。
だからこそ、想像する力はますます重要になります。
想像するからこそ、創り出せる。
想像するからこそ、他者に寄り添える。
想像するからこそ、自分なりの選択ができる。
AIがどれだけ進化しても、人間には人間にしかできないことがあります。
それは、「想像すること」。
この力を、私たちはもっと信じ、育てていくべきではないでしょうか。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください