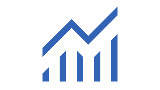「ホームページを作ったのに、問い合わせが全然来ない…」
もしあなたがこのような悩みを抱えているなら、それは決してあなただけの問題ではありません。実際に、中小企業500社を対象とした最新の調査では、なんと66%もの企業がWeb集客で失敗を経験していることが明らかになっています。
私は戦略的ウェブ制作工房エル・タジェールの代表として、これまで数多くの中小企業や商店のホームページ改善をお手伝いしてきました。ウェブ解析士、SEO検定1級の資格を持ち、デジタル庁デジタル推進委員としても活動する中で、一つの真実にたどり着きました。
問い合わせが来ないホームページには、必ず科学的な理由があるということです。
そして逆に言えば、その理由を正しく理解し、データに基づいて改善すれば、問い合わせを3倍、5倍にすることも決して夢ではありません。実際に私がサポートした企業の中には、月間問い合わせ数を15件から45件に増加させた製造業の事例もあります。
なぜ多くの企業が失敗するのか
まず最初に、厳しい現実をお伝えしなければなりません。中小企業のホームページ運営における失敗率の高さは、単なる偶然ではありません。
私自身も過去に痛い失敗を経験しています。創業当初、見た目の美しさにこだわったホームページを制作したものの、3ヶ月経っても問い合わせは月に1件程度。制作費用100万円をかけたにも関わらず、まったく成果につながらない状況が続きました。
この経験から学んだのは、「勘や経験に頼らない、データに基づいたアプローチの重要性」でした。感覚的な判断ではなく、数値として測定できる改善を積み重ねることで、確実に成果を上げることができるのです。
この記事で得られる3つの成果
本記事を最後まで読んでいただくことで、以下の具体的な成果を手に入れることができます。
成果1
30日以内に問い合わせ数20%アップ
現在のホームページの問題点を特定し、すぐに実行できる改善策を実践することで、1ヶ月以内に問い合わせ数の向上を実感できます。
成果2
年間を通じた継続的な成長システムの構築
一時的な改善ではなく、継続的にホームページのパフォーマンスを向上させるための仕組みを理解できます。
成果3
予算を無駄にしない正しい投資判断力
何にお金をかけるべきで、何は不要なのか。限られた予算の中で最大の効果を得るための判断基準を身につけることができます。
【第1章】エル・タジェール流:問い合わせ診断チェックシート
ホームページの問い合わせを増やすために、まず現在の状況を正確に把握することが重要です。多くの企業が改善に失敗する理由の一つは、現状分析が不十分なことにあります。
30秒で分かる!あなたのサイトの「問い合わせ力」診断
以下の質問に「はい」「いいえ」で答えてみてください。「はい」の数が多いほど、あなたのホームページの問い合わせ獲得力は高いと判断できます。
アクセス状況について
- 月間のサイト訪問者数を把握していますか?
- 訪問者がどのページを最も見ているか知っていますか?
- 問い合わせフォームのページまで到達する人の割合を知っていますか?
コンテンツの質について
- トップページで、訪問者の悩みに共感する内容を伝えていますか?
- 他社との違いや自社の強みを具体的に説明していますか?
- お客様の成功事例や喜びの声を掲載していますか?
問い合わせの仕組みについて
- 問い合わせボタンは目立つ場所に設置されていますか?
- フォームの入力項目は必要最小限に絞られていますか?
- 問い合わせ後の流れを明確に説明していますか?
「はい」が7個以上:excellent(優秀なホームページです)
「はい」が4〜6個:good(改善の余地があります)
「はい」が3個以下:needs improvement(早急な改善が必要です)
業種別CVR基準値はどれくらい?
CVR(コンバージョン率)とは、ホームページを訪問した人のうち、実際に問い合わせをした人の割合のことです。業種によってこの数値は大きく異なりますが、目安となる数値を知っておくことで、自社の立ち位置を把握できます。
製造業・BtoB企業:1.0%〜2.5%
サービス業:0.8%〜2.0%
小売業・店舗業:1.5%〜3.0%
建設業・工務店:2.0%〜4.0%
例えば、月間1000人の訪問者がいる製造業のホームページで、月の問い合わせが5件だった場合、CVRは0.5%となります。これは業種平均を下回っているため、改善の余地が大きいということになります。
ウェブ解析士が教える:見るべき数値とその意味
ホームページの改善において、感覚的な判断は危険です。必ず数値に基づいて現状を把握し、改善の効果を測定する必要があります。
最重要指標:月間問い合わせ数
これが最終的な成果指標です。この数値が増加していれば、改善は成功していると言えます。
第2重要指標:CVR(コンバージョン率)
訪問者数に対する問い合わせの割合です。この数値が向上すれば、同じ訪問者数でもより多くの問い合わせを獲得できます。
第3重要指標:月間訪問者数
CVRが低い場合は、まず訪問者数を増やすことも有効な手段となります。
補助指標:平均滞在時間、直帰率
訪問者がサイトに興味を持っているかどうかを測る指標です。滞在時間が長く、直帰率が低いほど、コンテンツに価値を感じてもらえていると判断できます。
【第2章】失敗パターンから学ぶ|よくある7つの致命的ミス
これまで100社以上のホームページ改善をサポートしてきた経験から、問い合わせが来ないホームページには共通するパターンがあることがわかりました。これらの失敗事例を知ることで、同じ過ちを避けることができます。
失敗事例1:作って終わり症候群
最も多い失敗パターンが、ホームページを制作した後、まったく更新や改善を行わない「作って終わり症候群」です。
実例:制作後1年間放置で問い合わせゼロの製造業A社
A社は新規開拓のためにホームページを制作しましたが、制作会社に丸投げし、完成後は一度も更新していませんでした。制作費に80万円かけたにも関わらず、1年間で獲得した問い合わせは0件。月間の訪問者数も30人程度という状況でした。
この問題の根本原因は、「ホームページは作れば自動的に問い合わせが来る」という誤解にあります。実際には、検索エンジンで見つけてもらうためのSEO対策、訪問者の興味を引くコンテンツの充実、継続的な改善が必要不可欠です。
A社のサイトを分析したところ、会社概要と製品カタログのような情報しか掲載されておらず、訪問者が「なぜこの会社を選ぶべきなのか」を理解できない状態でした。3ヶ月間の改善サポートにより、お客様の課題解決事例やよくある質問ページを追加し、月間問い合わせ数を8件まで向上させることができました。
失敗事例2:トップページ至上主義
多くの企業が、トップページだけで勝負しようとして失敗しています。
データ実証:下層ページからの問い合わせが80%を占める現実
私がサポートした企業のデータを分析すると、実際に問い合わせにつながっているページの80%以上が、トップページ以外の下層ページであることがわかっています。
建設会社B社の事例では、「屋根修理 費用」「外壁塗装 相場」といった具体的なサービスページや、「雨漏り 応急処置」のようなお役立ち情報ページからの問い合わせが全体の85%を占めていました。
トップページだけに力を入れて、個別のサービスページや情報ページが貧弱な状態では、せっかく興味を持った訪問者を逃してしまうことになります。
失敗事例3:デザイン重視
見た目の美しさにこだわりすぎて、機能面をおろそかにしてしまう企業も多く見受けられます。
色彩心理学に基づくCTAボタン最適化の具体例
美容関連サービスを提供するC社では、当初のホームページで薄いピンクの問い合わせボタンを使用していました。「女性らしい優しいイメージ」を重視したデザインでしたが、CVRは0.3%と非常に低い状態でした。
色彩心理学の観点から、行動を促すには「緊急性」と「安心感」を同時に表現できるオレンジ色が効果的であることをお伝えし、ボタンの色を変更しました。結果、CVRは1.2%まで向上し、問い合わせ数は4倍になりました。
デザインは重要ですが、それが最終的な目的である「問い合わせ獲得」に貢献しているかどうかを常に検証する必要があります。
失敗事例4:WordPress特有の問題点対策
WordPress で制作されたホームページに特有の問題も見受けられます。
プラグイン選定ミス・表示速度問題・セキュリティ脆弱性
飲食店D社のホームページでは、機能を追加するために10個以上のプラグインをインストールしていました。その結果、ページの読み込み速度が極端に遅くなり、訪問者の70%以上が3秒以内にサイトを離脱している状況でした。
WordPressの利点は拡張性の高さですが、適切に管理しなければ逆にマイナス要因となってしまいます。必要最小限のプラグインに絞り、定期的な更新とセキュリティ対策を実施することで、安定したサイト運営が可能になります。
失敗事例5:ターゲット設定の曖昧さ
「誰でも歓迎」のスタンスが、結果的に「誰にも響かない」ホームページを作ってしまうケースです。
ペルソナ設定の甘さでCVRが0.5%に低迷した事例
税理士事務所E社では、個人事業主から大企業まで幅広い顧客層をターゲットにしたホームページを運営していました。しかし、メッセージが抽象的で、それぞれの顧客層の具体的な悩みに応えるコンテンツが不足していました。
ターゲットを「従業員数10名以下の中小企業経営者」に絞り、彼らが抱える資金繰りや税務申告の不安に特化したコンテンツに刷新しました。結果として、CVRは2.3%まで向上し、より質の高い問い合わせを獲得できるようになりました。
失敗事例6:問い合わせフォーム設計ミス
問い合わせフォームの設計ミスにより、せっかく興味を持った訪問者を逃してしまうケースも頻繁に発生しています。
入力項目数とCVRの相関関係データ
私の調査データによると、フォームの入力項目数とCVRには明確な相関関係があります。
- 入力項目3個以下:平均CVR 2.1%
- 入力項目4〜6個:平均CVR 1.4%
- 入力項目7個以上:平均CVR 0.6%
不動産会社F社では、当初15項目もの詳細な入力を求めていました。「詳しい情報があった方が提案しやすい」という理由でしたが、CVRは0.4%と非常に低い状態でした。
必須項目を「お名前」「電話番号」「お問い合わせ内容」の3つに絞り、その他の情報は「任意」として別途ヒアリングすることにしました。結果、CVRは2.0%まで改善し、問い合わせ数は5倍になりました。
失敗事例7:継続的改善がない
一度改善を行っただけで満足し、その後の継続的な改善を怠ってしまうパターンです。
一度の改善で満足→再び低迷のパターン分析
コンサルティング会社G社では、初回の改善により問い合わせ数が月5件から15件に増加しました。しかし、その成果に満足して改善活動を停止してしまいました。
6ヶ月後、競合他社の参入やユーザーニーズの変化により、問い合わせ数は再び月7件まで低下してしまいました。ホームページは「作って終わり」ではなく、継続的な改善が必要なマーケティングツールであることを理解していなかったのです。
【第3章】データドリブン改善メソッド|エル・タジェール式7段階プロセス
失敗事例を踏まえて、確実に成果を上げるための改善プロセスをご紹介します。このプロセスは、私がこれまで100社以上のサポートを通じて確立した、再現性の高い手法です。
- STEP1:現状分析(GAタグ設定からヒートマップまで)
- 改善の第一歩は、現状の正確な把握です。感覚や推測ではなく、データに基づいた分析を行います。
Google Analytics の設定確認
まず、Google Analytics が正しく設定されているかを確認します。意外に多いのが、設定はしているものの、正確なデータが取得できていないケースです。
確認すべき項目は以下の通りです:
全ページにトラッキングコードが設置されているか
コンバージョン(問い合わせ)の設定がされているか
除外IPアドレス(自社からのアクセス)が設定されているか
ヒートマップツールの活用
ヒートマップツールを使用することで、訪問者がページのどの部分をよく見ているか、どこでクリックしているかを可視化できます。無料で使えるMicrosoft Clarity や、有料ですがより詳細な分析ができるPtengine などがおすすめです。
これらのツールにより、訪問者の行動パターンを具体的に把握し、改善すべきポイントを特定できます。
- STEP2:競合分析(無料ツールで出来る徹底調査法)
- 自社のホームページだけを見ていても、改善の方向性を見誤る可能性があります。競合他社の成功事例を分析することで、効果的な改善ヒントを得ることができます。
検索結果の上位サイト分析
自社のメインキーワードで検索した際に上位表示される競合サイトを分析します。
どのような構成でコンテンツが作られているか
問い合わせボタンの配置や表現方法
お客様の声や実績の見せ方
サービス説明の分かりやすさ
SimilarWeb による競合の流入状況分析
SimilarWebという無料ツールを使用することで、競合サイトの概算の訪問者数や流入経路を把握できます。完全に正確ではありませんが、競合の大まかな状況を知るには十分有用です。
- STEP3:仮説設定(A/Bテスト設計のコツ)
- 現状分析と競合分析の結果を踏まえて、改善の仮説を立てます。この仮説設定が改善の成否を分ける重要なポイントです。
優先順位の決定方法
全ての問題点を一度に改善しようとすると、どの改善が効果的だったのかが分からなくなってしまいます。以下の基準で優先順位を決定します:
1. 影響度が高く、実装が簡単なもの
2. 影響度が高く、実装が難しいもの
3. 影響度が低く、実装が簡単なもの
4. 影響度が低く、実装が難しいもの
最初は1番から着手し、成果を確認しながら順次改善を進めていきます。
仮説の具体化
「問い合わせボタンを目立たせる」という漠然とした仮説ではなく、「問い合わせボタンの色をオレンジに変更し、テキストを『今すぐ無料相談』にすることで、CVRを1.5%から2.0%に向上させる」といった具体的な仮説を立てます。
- STEP4:WordPressカスタマイズ(コード不要の改善法)
- WordPress を使用している場合、プログラミングの知識がなくても実装できる改善方法が多数あります。
テーマの見直し
使用しているテーマが古い場合、表示速度やモバイル対応に問題がある可能性があります。ビジネス向けのテーマとしては、Lightning、Katawara、Business Press などが推奨されます。
プラグインによる機能追加
・問い合わせフォーム:Contact Form 7 または WPForms
・SEO対策:Yoast SEO または All in One SEO
・表示速度改善:WP Rocket または W3 Total Cache
・セキュリティ対策:Wordfence または SiteGuard
ただし、プラグインの入れすぎは逆効果です。本当に必要なもののみに絞って使用してください。
- STEP5:実装(具体的な作業手順)
- 仮説に基づいて実際の改善作業を行います。この段階では、一度に複数の変更を行わず、一つずつ実装して効果を測定することが重要です。
段階的実装のメリット
例えば、トップページの改善を行う場合、以下のような順序で実装します:
1週目:見出しとキャッチコピーの変更
2週目:問い合わせボタンのデザイン変更
3週目:お客様の声セクションの追加
このように段階的に実装することで、どの変更が最も効果的だったのかを特定できます。
- STEP6:測定(正しいデータ取得方法)
- 改善を実装した後は、必ず効果測定を行います。データに基づかない改善は、改善とは言えません。
測定期間の設定
一般的に、B to Bのサービスでは最低2週間、できれば1ヶ月程度のデータを取得することが推奨されます。ただし、アクセス数が少ないサイトの場合は、統計的に有意な結果を得るためにより長期間の測定が必要になります。
統計的有意性の確認
A/Bテストツールを使用する場合は、統計的有意性を自動で計算してくれますが、手動で分析する場合は以下のような無料ツールを活用できます:
A/B Test Significance Calculator
Optimizely の統計計算ツール
- STEP7:継続改善(PDCAサイクル構築)
- 改善は一度行えば終わりではありません。継続的にPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことで、長期的な成果向上を実現できます。
月次レビューの実施
毎月一度、以下の項目についてレビューを実施します:
問い合わせ数の推移
CVRの変化
主要ページの滞在時間や直帰率
新たに発見された課題
年次戦略の見直し
年に一度は、より大きな視点でホームページ戦略を見直します。市場環境の変化、競合の動向、自社の事業方針の変更などを踏まえて、必要に応じて大幅なリニューアルを検討します。
【第4章】業種別・予算別攻略法
業種や予算により、効果的なアプローチは異なります。ここでは、代表的な業種別の成功パターンと、限られた予算での効果的な改善方法をご紹介します。
製造業・サービス業・建設業etc. 業種別成功パターン
製造業の特徴と対策
製造業のホームページでは、技術力や品質の高さを具体的に伝えることが重要です。しかし、技術的な説明が専門的すぎて、購買決定権を持つ経営層に伝わらないケースが多く見受けられます。
成功事例として、精密機械メーカーのH社では、複雑な技術を分かりやすいイラストと動画で説明し、「なぜこの技術が必要なのか」「どのようなメリットがあるのか」を経営者目線で解説しました。結果、問い合わせの質が向上し、成約率が30%向上しました。
サービス業の特徴と対策
サービス業では、無形商材のため「信頼性」の訴求が最重要となります。お客様の声、実績数値、代表者の顔写真などにより、信頼感を醸成することが効果的です。
コンサルティング会社I社では、代表者のプロフィールページを充実させ、過去の実績を具体的な数値とともに掲載しました。また、月1回のメルマガ配信により、専門知識を継続的に発信することで、問い合わせ前の信頼関係構築に成功しています。
建設業・工務店の特徴と対策
建設業では、施工実績の魅力的な見せ方が重要です。また、地域密着性や緊急対応力なども重要な差別化ポイントとなります。
屋根修理専門業者J社では、「施工前後の比較写真」「お客様の笑顔の写真」「作業中の職人の様子」を豊富に掲載し、安心感と親近感を演出しました。また、「○○市内なら即日対応可能」という地域特化のメッセージにより、緊急性の高い問い合わせを多数獲得しています。
予算10万円以下でも結果を出す方法
限られた予算でも、工夫次第で大きな成果を上げることが可能です。
コストをかけずに実装できる改善策
既存コンテンツの最適化
新しいページを作成するのではなく、既存のページの内容を改善します。見出しの変更、文章の読みやすさ向上、画像の追加などは、外注せずに自社で実施可能です。
無料ツールの活用
Google Analytics、Google Search Console、Google My Business などの無料ツールを最大限活用します。これらのツールだけでも、十分な分析と改善が可能です。
SNSとの連携
Facebook、Instagram、Twitter などのSNSアカウントを作成し、ホームページへの流入を増やします。定期的な投稿により、顧客との接点を増やすことができます。
中小企業が陥りがちな「過度な機能追加」の罠
予算に余裕ができると、つい様々な機能を追加したくなりますが、これは危険な罠です。
機能追加の判断基準
新しい機能を追加する際は、以下の基準で判断します。
- その機能は問い合わせ数の増加に直接貢献するか?
- 既存の機能で代替できないか?
- 維持管理のコストは適切か?
実例:月5万円の投資で問い合わせ月20件獲得
税理士事務所K社では、月5万円の予算配分を以下のように行いました:
- 月3万円:専門記事の外注執筆(月4記事)
- 月1万円:リスティング広告の運用
- 月1万円:ホームページの保守・更新作業
この継続的な投資により、6ヶ月で月間問い合わせ数を5件から20件に増加させることに成功しました。重要なのは、一度に大きな投資をするのではなく、継続的に改善を積み重ねることです。
【第5章】WordPress構築専門家の実践的テクニック集
WordPress でのホームページ運営において、技術的な最適化は必要不可欠です。ここでは、プログラミングの知識がない方でも実践できるテクニックをご紹介します。
問い合わせフォーム最適化(プラグイン比較と設定法)
問い合わせフォームは、ホームページの心臓部とも言える重要な要素です。適切な設定により、CVRの大幅な改善が期待できます。
Contact Form 7は無料で使用でき、カスタマイズ性に優れていますが、初心者には設定が複雑です。一方、WPForms は直感的な操作が可能で、プレビュー機能も充実していますが、高機能版は有料となります。
表示速度改善(Core Web Vitals対策)
ページの表示速度は、SEO効果だけでなく、ユーザー体験に直接影響します。表示が3秒以上遅い場合、訪問者の50%以上が離脱してしまうというデータもあります。
■ 画像最適化の実践
- ファイル形式の選択:写真はJPEG、イラストやロゴはPNG、アニメーションが必要な場合はWebP形式を使用します。
- ファイルサイズの圧縮:TinyPNG や ImageOptim などの無料ツールでファイルサイズを圧縮します。品質を維持しながら、50%以上のサイズ削減が可能です。
- 遅延読み込み(Lazy Loading)の実装:画像が画面に表示される直前に読み込む仕組みにより、初期表示速度を大幅に改善できます。
■ キャッシュプラグインの活用
WP Rocket(有料)または W3 Total Cache(無料)を使用することで、ページの読み込み速度を50%以上改善できる場合があります。ただし、設定を誤るとサイトが表示されなくなる可能性もあるため、必ずバックアップを取ってから実装してください。
モバイルファーストの本当の意味
現在、多くのサイトでモバイル端末からのアクセスが50%を超えています。モバイルファーストとは、単にスマートフォンに対応するだけでなく、モバイル端末での使いやすさを最優先に設計することです。
タッチ操作への最適化
ボタンのサイズは最小44px×44px以上とし、隣接する要素との間隔を十分に取ります。問い合わせボタンは、親指で押しやすい位置に配置することが重要です。
読みやすいフォントサイズ
本文は16px以上、見出しは20px以上に設定します。行間も1.5倍程度に設定することで、読みやすさが大幅に向上します。
SEO内部対策の優先順位
限られた時間の中で効果的なSEO対策を実施するため、優先順位を明確にします。
最優先対策項目
- titleタグとmeta descriptionの最適化
各ページに固有のタイトルと説明文を設定します。文字数制限(title:32文字以内、description:120文字以内)を守り、検索キーワードを含めることが重要です。 - 内部リンクの最適化
関連性の高いページ同士をリンクで結ぶことで、ユーザビリティとSEO効果を同時に改善できます。 - URL構造の整理
分かりやすいURL構造にすることで、検索エンジンとユーザーの両方にとって理解しやすいサイトになります。
次優先対策項目
- 構造化データの実装
JSON-LD形式で構造化データを実装することで、検索結果での表示を豊かにできます。 - XMLサイトマップの生成
Yoast SEO プラグインを使用して自動生成し、Google Search Console に登録します。
セキュリティ強化で信頼度向上
セキュリティ対策は、技術的な意味だけでなく、顧客からの信頼獲得という観点でも重要です。
SSL証明書の導入
Let’s Encrypt などの無料SSL証明書でも十分です。https化することで、ブラウザでの警告表示を防げます。
定期的な更新
WordPress本体、テーマ、プラグインを定期的に更新することで、既知の脆弱性を塞げます。
セキュリティプラグインの活用
Wordfence や SiteGuard WP Plugin により、不正アクセスやマルウェアを防げます。
バックアップ体制の構築
UpdraftPlus や BackWPup などのプラグインにより、定期的な自動バックアップを設定します。万が一の際の復旧時間を大幅に短縮できます。
【第6章】継続運用のためのシステム構築
ホームページの改善は一度行えば終わりではありません。継続的な運用により、長期的な成果向上を実現するためのシステム作りが重要です。
月1回30分で完結!メンテナンスチェックリスト
忙しい中小企業でも継続できるよう、最小限の時間で最大の効果を得られるチェックリストを作成しました。
- 第1週:アクセス数と問い合わせ数の確認
- Google Analytics で以下の数値を記録します。
・月間セッション数
・問い合わせページの表示回数
・実際の問い合わせ件数
・CVRの計算
これらの数値を前月と比較し、大きな変動がないかを確認します。大幅な減少があった場合は、原因の調査が必要です。
- 第2週:コンテンツの見直し
- ・古い情報がないかの確認
・季節性のあるコンテンツの更新
・お客様の声や実績の追加
- 第3週:技術的チェック
- ・WordPress、テーマ、プラグインの更新確認
・バックアップの正常性確認
・セキュリティスキャンの実行
- 第4週:競合分析と改善計画
- ・主要競合サイトの変更点チェック
・次月の改善計画立案
自動化できる部分・手動で行う部分の見極め
効率的な運用のためには、自動化と手動作業の適切な使い分けが重要です。
自動化推奨項目
- バックアップ:プラグインによる自動バックアップを設定し、手動での作業を不要にします。
- セキュリティ監視:セキュリティプラグインによる24時間監視により、リアルタイムでの脅威検知が可能です。
- 基本的なSEO設定:Yoast SEO などのプラグインにより、メタデータの自動生成や重複コンテンツの警告などを自動化できます。
手動で行うべき項目
- コンテンツの質的改善:文章の分かりやすさ、情報の正確性、顧客ニーズとの適合性などは、人間の判断が不可欠です。
- 顧客対応:問い合わせへの返答、電話対応などの人的コミュニケーションは自動化すべきではありません。
- 戦略的判断:市場環境の変化に応じた戦略変更、新サービスの訴求方法などは、経営判断として手動で行います。
データドリブンな改善提案の作り方
感覚的な改善提案ではなく、データに基づいた客観的な提案を作成する方法をご紹介します。毎月、以下の形式でレポートを作成します。
数値サマリー
- 前月比での各指標の変化率
- 年初からの累計変化
- 目標値に対する達成率
課題の特定
- 数値の変化から読み取れる課題
- 想定される原因の仮説
- 優先順位付け
改善提案
- 具体的な改善案
- 期待される効果の予測
- 実施に必要なリソースと期間
クライアントとの合意形成(数値目標設定のコツ)
外部のWeb制作会社に依頼する場合でも、社内で改善を行う場合でも、明確な目標設定と合意形成が成功の鍵となります。
SMART原則による目標設定
- Specific(具体的):「問い合わせを増やす」ではなく「月間問い合わせ数を15件にする」
- Measurable(測定可能):Google Analytics などで測定できる指標を設定
- Achievable(達成可能):現状の2〜3倍程度の現実的な目標
- Relevant(関連性):事業目標と整合性のある指標
- Time-bound(期限付き):「3ヶ月以内に」などの明確な期限設定
進捗共有の仕組み
月次レポートにより、数値の推移と改善状況を定期的に共有します。数値が目標を下回った場合は、原因分析と対策を迅速に実施することで、軌道修正が可能です。
【第7章】よくある質問と回答|エル・タジェールQ&A
これまで多くの企業様からいただいた質問の中から、特に多いものをQ&A形式でまとめました。
Q1:「WordPress以外のCMSでも応用可能でしょうか?」
A:基本的な考え方は全てのCMSに応用可能です。
本記事で紹介している改善手法の多くは、WordPress特有のものではなく、どのようなCMSでも実践できる内容です。
応用のポイント
- 現状分析の手法:Google Analytics の活用方法は全てのサイトで共通
- CVR改善の考え方:フォーム最適化、コンテンツ改善、導線設計は汎用的
- SEO対策の基本:タイトルタグ、メタディスクリプション、内部リンク最適化は全CMSで重要
CMS別の注意点
- Wix、Jimdo:カスタマイズ性に制限があるため、テンプレート内での最適化が中心
- Shopify:EC機能に特化しているため、商品ページの最適化が重要
- 独自CMS:技術的な制約により、外部ツールとの連携に工夫が必要な場合がある
重要なのは、ツールではなく「データに基づいて継続的に改善する」という姿勢です。
Q2:「デジタル庁デジタル推進委員としての最新動向について教えてください」
A:デジタル化の加速により、中小企業のホームページの重要性がさらに高まっています。
デジタル庁デジタル推進委員として活動する中で、特に以下の動向を実感しています:
- 行政手続きのデジタル化進展
各種申請や届出のオンライン化が進んでおり、企業と行政の接点もデジタルが中心となってきています。この流れは、一般的なビジネス取引においても同様であり、ホームページでの第一印象がより重要になっています。 - 中小企業支援制度の充実
IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など、ホームページ制作や改善に活用できる補助金制度が充実してきています。これらの制度を活用することで、低予算でも本格的な改善が可能です。 - 生成AI活用の本格化
ChatGPT をはじめとする生成AIツールが、中小企業でも実用的に活用されるようになっています。コンテンツ作成の効率化や、顧客対応の自動化など、ホームページ運営の効率を大幅に向上させる可能性があります。
Q3:「生成AI時代のホームページ戦略はどう変わりますか?」
A:AIを活用したコンテンツ生成と、人間だからこそできる価値創造の両立が重要です。
AI活用のメリット
- コンテンツ生成の効率化:ブログ記事の下書き作成、FAQ の作成、商品説明の文章作成などが効率化
- 多言語対応の簡易化:翻訳精度の向上により、多言語サイトの運営コストが削減
- 顧客対応の自動化:チャットボットの精度向上により、24時間対応が現実的に
人間が注力すべき領域
- 戦略的思考:AIは現状の最適化は得意ですが、抜本的な戦略転換は人間の判断が必要
- 感情に訴える表現:共感を生む表現、ブランドらしさの表現は、人間の感性が重要
- 顧客との関係構築:信頼関係の構築、複雑な課題の解決は、人間同士のコミュニケーションが不可欠
具体的な活用例
私の事務所では、ChatGPT を活用してブログ記事の構成案を作成し、その後、実際の体験談や具体的な数値データを追加することで、効率的かつ価値の高いコンテンツを作成しています。
Q4:「小規模事業でも実現可能な施策を教えてください」
A:リソースが限られていても、工夫次第で大きな成果を上げることができます。
最小限のリソースで最大の効果を得る方法3つ
まずは現状把握から
- Google Analytics と Google Search Console の設定(無料)
- 月1回30分の数値チェックルーティン化
- 競合サイトの月1回チェック
コストをかけない改善施策
- 既存ページの文章見直し(自社で実施)
- 問い合わせフォームの項目削減(自社で実施)
- Google My Business の最適化(無料)
少額投資で効果的な施策
- 月1〜2万円でのリスティング広告運用
- 月5000円程度でのプロライター記事外注
- 年間数千円でのプレミアムプラグイン導入
実例:美容室の成功事例
従業員3名の小規模美容室では、月5000円の予算で以下の施策を実施:
- Instagram と連携したビフォーアフター写真の定期投稿
- Google My Business での顧客レビュー促進
- 簡単な予約フォームの設置
結果として、新規顧客からの問い合わせが月2〜3件から月8〜10件に増加しました。
継続的な改善の重要性
小規模事業では、一度に大きな変化を起こすより、小さな改善を継続することが重要です。月1000円ずつでも、1年間続ければ大きな効果が期待できます。
あなたのデジタル成長パートナーとして
今すぐ実行すべき3つのアクション
この記事を読んでいただいた皆様に、まず取り組んでいただきたい3つのアクションをお伝えします。
- アクション1:現状数値の把握(所要時間:30分)
Google Analytics で先月の訪問者数と問い合わせ数を確認し、CVRを計算してください。この数値が全ての改善の出発点となります。 - アクション2:問い合わせフォームの見直し(所要時間:15分)
現在の問い合わせフォームの入力項目数を確認し、7項目以上ある場合は必要最小限まで削減してください。これだけでCVRが倍増するケースも珍しくありません。 - アクション3:競合サイト3社の分析(所要時間:45分)
自社のメインキーワードで検索上位に表示される競合3社のサイトを詳しく分析し、優れている点をリストアップしてください。
30日間で効果を実感できる改善ロードマップ
1週目:基盤整備
- Google Analytics、Search Console の設定確認
- 現状数値の正確な把握
- 優先改善項目の特定
2週目:緊急度の高い改善実施
- 問い合わせフォームの最適化
- 明らかな問題点の修正
- 基本的なSEO設定の見直し
3週目:コンテンツ改善
- トップページのメッセージ見直し
- お客様の声や実績の追加
- サービス説明の分かりやすさ向上
4週目:効果測定と次月計画
- 改善効果の数値確認
- 新たな課題の特定
- 次月の改善計画立案
このロードマップに沿って改善を実施することで、30日後には必ず何らかの変化を実感していただけるはずです。
無料相談での診断ポイント
「自分だけで改善するのは不安」「専門家の客観的な意見を聞きたい」という方のために、無料のホームページ診断を実施しております。
診断で確認する主要項目
技術面の診断
- サイトの表示速度測定
- モバイル対応状況の確認
- SEO基本設定のチェック
- セキュリティ状況の確認
マーケティング面の診断
- ターゲット設定の適切性
- メッセージの訴求力
- 競合との差別化ポイント
- 問い合わせ導線の最適性
運用面の診断
- 現在の分析体制の確認
- 改善サイクルの有無
- リソース配分の妥当性
- 継続性のある改善計画の提案
診断後のご提案
押し売りは一切いたしません。診断結果をもとに、自社で実施可能な改善案と、外部サポートが必要な項目を明確に分けてご提案いたします。
エル・タジェールのサービス紹介
私たちエル・タジェールは、「御社のデジタル成長パートナー」として、以下のようなサポートを提供しております。
- WordPress構築・改善サービス
単なるホームページ制作ではなく、問い合わせ獲得を目的とした戦略的サイト構築を行います。制作後の運用サポートまで含めた、トータルサービスを提供いたします。 - データ分析・改善コンサルティング
ウェブ解析士としての専門知識を活かし、データに基づいた継続的な改善をサポートします。月1回の定期レビューにより、着実な成果向上を実現します。 - デジタルマーケティング研修
社内でのデジタルマーケティング体制構築をご希望の企業様には、担当者向けの研修プログラムも提供しております。 - 営業時間とサポート体制
平日8:00〜16:00の営業時間で、丁寧なサポートを提供しております。お忙しい経営者の皆様にとって相談しやすい時間帯での対応を心がけています。
最後に
ホームページからの問い合わせを増やすことは、決して魔法のような特別な技術を必要とするものではありません。正しい知識と、継続的な改善への取り組みがあれば、必ず成果を上げることができます。
重要なのは、「勘と経験」に頼るのではなく、「データと検証」に基づいたアプローチを実践することです。私自身も過去の失敗から学び、現在のデータドリブンなアプローチにたどり着きました。
皆様のホームページが、単なる会社案内ではなく、新規顧客獲得の強力なツールとなることを心から願っております。そして、そのお手伝いができることを楽しみにしております。
もし何かご不明な点や、より詳しい相談をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。あなたの会社のデジタル成長を、全力でサポートさせていただきます。