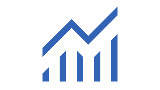「ホームページを作ったけれど、全然お問い合わせが来ない…」「制作費用に見合った効果が感じられない…」そんな悩みを抱えている中小企業の経営者や店舗オーナーの方は少なくありません。
実際、私がウェブ解析士として多くの企業サイトを診断してきた経験では、約7割の中小企業ホームページが本来の目的を果たせずにいる現状があります。その多くは、制作段階での「やってはいけないこと」を知らずに進めてしまったことが原因です。
この記事では、ウェブ解析士・SEO検定1級の資格を持ち、WordPress構築専門家として数多くの中小企業サイトを手掛けてきた私が、2025年現在において絶対に避けるべきホームページ制作の注意点を15項目に絞ってお伝えします。これらの注意点を知ることで、あなたの会社のホームページが「作っただけで終わり」ではなく、しっかりと成果につながるものになるでしょう。
ホームページ制作で失敗する企業の共通点
まず理解していただきたいのは、ホームページ制作の失敗には明確なパターンがあるということです。私がこれまで診断してきた企業の中で、成果の出ないホームページには必ずと言っていいほど共通する問題があります。
最も多いのは「作ることが目的になってしまっている」ケースです。デザインや機能にばかり注目し、「誰に」「何を」「どのような形で」伝えるのかという本質的な部分が曖昧なまま制作を進めてしまうのです。
また、制作後の運用や改善を考えずに「完成品」として扱ってしまうことも大きな問題です。ホームページは公開してからが本当のスタートであり、データを見ながら継続的に改善していくものです。この認識がないと、せっかく投資した制作費用が無駄になってしまいます。
【戦略編】基本設計で犯しがちな致命的な間違い
注意点1
測定不可能な目標設定をしてしまう
「おしゃれなホームページにしたい」「会社のイメージを良くしたい」といった抽象的な目標設定は、ホームページ制作における最大の落とし穴です。これらの目標は一見もっともらしく聞こえますが、実際には成功したかどうかを判断することができません。
正しい目標設定とは、具体的な数値で表現できるものです。例えば「月間お問い合わせ件数を現在の3件から10件に増やす」「資料請求のコンバージョン率を2%以上にする」といった形です。これらの目標があることで、ホームページの構成やデザイン、コンテンツの方向性が明確になります。
さらに重要なのは、これらの目標を測定するための仕組みを最初から組み込んでおくことです。Googleアナリティクス4(GA4)の適切な設定により、訪問者の行動を詳細に把握し、目標達成度を正確に測定できます。多くの制作会社は基本的なアクセス解析の設定しか行いませんが、本当に成果を上げるためには、コンバージョン設定やイベント設定まで含めた詳細な解析環境が必要です。
注意点2
ペルソナの検索行動を無視してしまう
ターゲット設定は多くの企業が行いますが、そのペルソナが「実際にどのような言葉で検索するか」まで考えられているケースは驚くほど少ないのが現実です。年齢や性別、職業といった属性情報だけでは、効果的なホームページは作れません。
例えば、地域の工務店の場合を考えてみましょう。同じ「家を建てたい人」でも、初回検索時には「注文住宅 ○○市」で検索し、比較検討段階では「工務店 評判」「施工事例 価格」といったより具体的なキーワードで検索します。さらに、決定間近になると「○○工務店 口コミ」のような指名検索に変わります。
この検索行動の変化を理解せずにサイト設計を行うと、せっかく訪問してくれたユーザーに適切な情報を提供できず、競合他社に流れてしまいます。検索キーワードごとに最適なコンテンツを用意し、ユーザーの検索意図に応える構成にすることが重要です。
注意点3
競合サイトのSEO分析を怠る
自社のホームページを制作する際、競合他社のサイトをチェックしない企業は論外ですが、表面的な確認だけで終わってしまうケースも多く見られます。真に重要なのは、競合サイトがどのようなSEO戦略を取り、どのキーワードで上位表示を獲得しているかを分析することです。
無料ツールを使っても、競合サイトの基本的なSEO状況は把握できます。例えば、競合サイトのタイトルタグやメタディスクリプション、見出し構造、使用している画像のalt属性まで詳細に分析することで、自社サイトでどの部分に力を入れるべきかが見えてきます。
また、競合サイトのコンテンツ戦略も重要な分析対象です。どのようなブログ記事を投稿し、どの程度の頻度で更新しているか。お客様の声や施工事例などをどのように見せているか。これらの分析から、自社が差別化できるポイントが明確になります。
【制作会社選定編】騙されやすい営業トークの実態
注意点4
GA4対応できない制作会社を選んでしまう
2023年7月にGoogleアナリティクスの旧版(ユニバーサルアナリティクス)が完全に終了し、現在はGA4が標準となっています。しかし、驚くことに多くの制作会社がまだGA4の適切な設定方法を理解していません。
GA4は従来のアクセス解析とは大きく異なる仕組みで動作するため、正しく設定するには専門的な知識が必要です。単にトラッキングコードを埋め込むだけでは、ビジネスに必要なデータを取得できません。コンバージョン設定、イベント設定、カスタムディメンションの設定など、複数の要素を適切に組み合わせて初めて有効な分析が可能になります。
制作会社を選定する際は、「GA4の設定はどこまで対応していただけますか?」「コンバージョン測定の設定は含まれていますか?」といった具体的な質問をすることをお勧めします。曖昧な回答しかできない制作会社は、実際のGA4対応能力に疑問があると考えた方が良いでしょう。
注意点5
「SEO対策込み」の曖昧な提案を鵜呑みにしてしまう
多くの制作会社が「SEO対策もセットで行います」と提案してきますが、その内容を詳しく聞いてみると、基本的なタイトルタグの設定程度しか含まれていないケースが大半です。本当に効果的なSEO対策は、キーワード調査から始まり、競合分析、コンテンツ戦略の立案、技術的な最適化まで多岐にわたります。
特に注意すべきは「必ず上位表示させます」といった誇大な約束をする業者です。検索エンジンのアルゴリズムは常に変化しており、特定のキーワードでの上位表示を保証することは不可能です。信頼できる制作会社は、現実的な目標設定と、長期的な改善プロセスについて誠実に説明してくれます。
SEO対策の提案を受ける際は、「具体的にどのキーワードを狙うのか」「どのような手法で対策を行うのか」「効果測定はどのように行うのか」といった詳細を確認することが重要です。
注意点6
保守運用体制が不明確な会社を選んでしまう
ホームページは制作して終わりではありません。セキュリティアップデート、コンテンツの更新、システムの保守など、継続的な運用が必要です。しかし、制作会社の中には制作のみに特化しており、運用サポートが手薄な会社も存在します。
運用体制について確認すべき点は多岐にわたります。まず、定期的なバックアップは実施されるか。WordPressなどのCMSやプラグインのアップデートはどの頻度で行われるか。万が一サイトに問題が発生した場合の対応時間はどの程度か。これらの点を事前に明確にしておかないと、後々トラブルの原因になります。
また、月次レポートの提供についても重要なポイントです。アクセス数やお問い合わせ数などの基本的な数値だけでなく、改善提案や次月の施策についても含まれているかを確認しましょう。データを提供するだけでなく、そのデータを基にした具体的なアクションプランを提示してくれる制作会社を選ぶことが重要です。
【技術編】2025年に必須の技術要件
注意点7
Core Web Vitalsを無視してしまう
GoogleはPage Experience Update以降、サイトの表示速度やユーザビリティを検索順位の重要な要素として評価しています。中でもCore Web Vitalsと呼ばれる指標は、2025年現在のSEOにおいて無視できない要素となっています。
Core Web Vitalsは、LCP(Largest Contentful Paint)、FID(First Input Delay)、CLS(Cumulative Layout Shift)の3つの指標で構成されています。これらは簡単に言うと、「ページの読み込み速度」「操作への応答速度」「表示の安定性」を測定するものです。
多くの中小企業サイトでこれらの指標が基準値を下回っているのは、制作段階でCore Web Vitalsを考慮していないことが原因です。画像の最適化、不要なプラグインの削除、サーバーの性能向上など、技術的な最適化を行うことで大幅な改善が可能です。
PageSpeed Insightsなどの無料ツールを使用すれば、自社サイトの現状を把握できます。もし赤色や黄色の評価が表示されている場合は、早急な改善が必要です。
注意点8
WordPressセキュリティ対策を怠る
WordPressは世界中のウェブサイトの約4割で使用されている人気のCMSですが、その普及率の高さゆえにハッカーの標的にもなりやすいシステムです。適切なセキュリティ対策を講じていないWordPressサイトは、不正アクセスやマルウェア感染のリスクにさらされています。
基本的なセキュリティ対策には、WordPressコア、テーマ、プラグインの定期的なアップデート、強固なパスワードの設定、不要なプラグインの削除などがあります。さらに、セキュリティプラグインの導入、ログイン試行回数の制限、管理画面へのアクセス制限なども重要な対策です。
実際に私が診断した中小企業サイトの中には、数年間アップデートを行っていないWordPressサイトが数多く存在していました。これらのサイトは、セキュリティホールを放置している状態であり、いつ攻撃を受けてもおかしくない危険な状況です。
セキュリティ対策は一度設定すれば終わりではなく、継続的な監視と更新が必要です。制作会社にセキュリティ対策について質問する際は、具体的にどのような対策を実施するのか、運用開始後のセキュリティメンテナンスはどのように行うのかを確認することが重要です。
注意点9
モバイルファースト設計を軽視してしまう
「うちはBtoB企業だからスマートフォン対応はそれほど重要ではない」と考えている経営者の方もいらっしゃいますが、これは大きな誤解です。2025年現在、業種を問わずスマートフォンからのアクセスが全体の6割以上を占めるケースが一般的になっています。
Googleも2018年からモバイルファーストインデックスを開始しており、スマートフォン版のサイトを基準に検索順位を決定しています。つまり、スマートフォンで見づらいサイトは検索順位でも不利になってしまうのです。
モバイルファースト設計とは、単にスマートフォンでも表示できるということではありません。スマートフォンの小さな画面でも読みやすい文字サイズ、タップしやすいボタンサイズ、スクロールしやすいレイアウトなど、モバイルユーザーの使いやすさを最優先に考えた設計が必要です。
特に、お問い合わせフォームはモバイル対応が重要です。入力項目が多すぎたり、入力しづらいデザインになっていたりすると、せっかく関心を持ってくれたユーザーを逃してしまいます。
【コンテンツ・法務編】知らないでは済まされないリスク
注意点10
景品表示法・薬機法の規制を無視してしまう
ホームページのコンテンツ制作において、法的規制への対応は避けて通れない重要な課題です。特に2023年10月からはステルスマーケティング(ステマ)が景品表示法の規制対象となり、広告であることを明確に表示することが義務化されました。
中小企業でよく見られる問題は、お客様の声や口コミを掲載する際の表記不備です。実際の顧客による感想であっても、謝礼を支払って投稿してもらった場合は「広告」として表示する必要があります。また、「No.1」「最高級」といった表現を使用する場合は、その根拠となるデータの明示が必要です。
健康食品、化粧品、医療機器などを扱う企業では、薬機法(旧薬事法)の規制にも注意が必要です。効果効能を謳う表現は薬機法違反となる可能性があり、行政処分や刑事処罰の対象になることもあります。
これらの法的リスクを回避するためには、業界ごとの規制内容を正確に理解し、適切な表現を使用することが重要です。不安な場合は、コンテンツ制作前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。
注意点11
著作権フリーでない素材を使用してしまう
インターネット上にある画像や動画は、自由に使用できるものではありません。著作権者の許可なく使用すると、著作権侵害として法的責任を問われる可能性があります。この問題は、制作を外部に依頼した場合でも発注者側の責任になることが多いため、特に注意が必要です。
安全に画像を使用するためには、商用利用可能な素材サイトを利用することが重要です。無料の素材サイトでも商用利用可能なものは多数ありますが、利用規約をしっかりと確認することが必要です。また、クレジット表記が必要な素材もあるため、使用前には必ず利用条件を確認しましょう。
最も安全なのは、自社で撮影したオリジナルの写真を使用することです。商品写真、店舗の外観・内観、スタッフの写真など、自社で撮影した素材を使用することで、著作権の問題を回避できるだけでなく、他社との差別化も図れます。
近年は、AI生成画像の使用に関する議論も活発になっています。AI生成画像を使用する場合は、学習データに含まれた既存作品の著作権との関係や、プラットフォームの利用規約を慎重に確認することが重要です。
注意点12
E-E-A-Tを考慮しないコンテンツを作ってしまう
GoogleはE-E-A-T(Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)を重要な評価基準としています。これは「経験」「専門性」「権威性」「信頼性」を表しており、特に健康、金融、法律などのYMYL(Your Money or Your Life)分野では厳格に評価されます。
多くの中小企業サイトで見られる問題は、コンテンツの作成者が不明確であることです。「誰が」「どのような経験や資格に基づいて」その情報を発信しているのかが明確でないと、Googleからの評価が低くなってしまいます。
E-E-A-Tを向上させるためには、まず作成者情報を明確にすることが重要です。代表者のプロフィール、保有資格、業界経験年数、実績などを詳細に掲載しましょう。また、外部サイトからの言及(被リンクや口コミ)も権威性向上に寄与します。
さらに、コンテンツの正確性を担保するため、情報源の明示や定期的な内容更新も重要です。古い情報をそのまま放置しておくと、信頼性の評価が下がってしまいます。
【SEO・運用編】継続的な成果を生み出すために
注意点13
ローカルSEO対策を軽視してしまう
地域密着型のビジネスを行っている企業にとって、ローカルSEO対策は売上に直結する重要な施策です。しかし、多くの中小企業がGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の活用を十分に行えていないのが現状です。
ローカルSEOの基本は、Googleビジネスプロフィールの情報を正確かつ詳細に登録することです。営業時間、住所、電話番号、サービス内容などの基本情報はもちろん、写真の投稿、お客様からの口コミへの返信なども重要な要素です。
また、ホームページ内でのローカル情報の最適化も欠かせません。NAP情報(Name、Address、Phone)をサイト内で統一し、地域名を含むキーワードで最適化を行うことで、地域検索での上位表示が期待できます。
「○○市 ○○店」「○○地域 ○○サービス」といったキーワードでの検索時に、自社サイトとGoogleビジネスプロフィールの両方が表示されることで、より多くの見込み客にアプローチできます。
注意点14
データ分析なしで運用してしまう
ホームページを公開した後、アクセス解析を全く見ていない企業が驚くほど多く存在します。これは非常にもったいない状況です。データを見ることで、想定していたターゲットが実際に訪問しているか、どのページがよく見られているか、どこで離脱しているかなど、改善のヒントが多数得られます。
GA4では、リアルタイムでユーザーの行動を把握できるだけでなく、期間を指定した詳細な分析も可能です。月ごとの訪問者数の変化、人気コンテンツの推移、コンバージョンに至るまでのユーザー行動など、ビジネスの改善に直結するデータが取得できます。
重要なのは、データを見るだけでなく、そこから仮説を立てて改善施策を実行することです。例えば、特定のページで離脱率が高い場合は、コンテンツの見直しやナビゲーションの改善を検討します。お問い合わせフォームでの離脱が多い場合は、入力項目の削減や入力支援機能の追加を行います。
月に一度は必ずデータを確認し、改善点を見つけて実行するというサイクルを確立することが、継続的な成果向上につながります。
注意点15
Search Consoleデータを活用しない
GoogleサーチコンソールはGoogleが無料で提供している分析ツールですが、その価値を理解していない企業が多いのが現状です。サーチコンソールでは、実際にどのような検索キーワードで自社サイトが表示され、どの程度クリックされているかを詳細に把握できます。
特に注目すべきは「検索パフォーマンス」のデータです。ここでは、検索キーワードごとの表示回数、クリック数、CTR(クリック率)、平均掲載順位が確認できます。このデータを分析することで、どのキーワードで上位表示を狙うべきか、どのページのタイトルを改善すべきかなどの具体的な施策が見えてきます。
例えば、表示回数は多いがクリック率が低いキーワードがあれば、そのページのタイトルやメタディスクリプションを改善することでアクセス数向上が期待できます。逆に、クリック率は高いが掲載順位が低いキーワードがあれば、そのページのコンテンツを充実させることで上位表示を狙えます。
また、サーチコンソールではサイトの技術的な問題も確認できます。クロールエラー、インデックス登録の問題、モバイルユーザビリティの問題など、SEOに影響する要素を早期に発見して対処することが可能です。
まとめ:成果につながるホームページ制作のために
ここまで15の注意点をお伝えしてきましたが、これらすべてに共通するのは「ユーザー目線に立って、データに基づいた改善を継続する」という基本的な考え方です。
ホームページは作って終わりではありません。公開後のデータ分析、ユーザーの声の収集、継続的な改善施策の実行など、運用フェーズでの取り組みが成果を左右します。
特に中小企業においては、限られた予算と人的リソースの中で最大の効果を上げる必要があります。そのためには、闇雲に施策を実行するのではなく、データに基づいた戦略的なアプローチが不可欠です。
もし、これらの注意点を読んで「自社のホームページは大丈夫だろうか?」と不安に感じられた場合は、一度専門家による診断を受けることをお勧めします。現状の問題点を明確にし、具体的な改善プランを立てることで、ホームページを真の営業ツールとして活用できるようになるでしょう。
デジタル時代において、ホームページは企業の顔であり、重要な営業ツールです。適切な制作プロセスを踏み、継続的な改善を行うことで、必ず成果につながるはずです。あなたの会社のデジタル成長のため、まずは現状把握から始めてみてはいかがでしょうか。