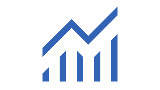「WordPressのユーザー権限って、結局どう設定すればいいの?」
そんな疑問を抱えている中小企業のホームページ担当者の方は多いのではないでしょうか。私は「戦略的ウェブ制作工房 エル・タジェール」代表として、これまで数多くの中小企業様のWordPressサイト制作・運用をサポートしてきました。
その中で痛感するのは、ユーザー権限の設定ミスが原因で深刻なトラブルに発展するケースが後を絶たないことです。情報処理推進機構(IPA)の2024年度実態調査によると、約7割の中小企業で組織的なセキュリティ体制が整備されておらず、権限管理の不備が情報漏洩やシステム障害の原因となっています。
実際に私がサポートしたケースでも、「アルバイトスタッフが誤ってプラグインを削除してサイトが表示されなくなった」「退職した従業員のアカウントが残ったままで情報漏洩リスクが発生した」といった事例を数多く見てきました。
しかし、適切なユーザー権限の設定と管理ができれば、これらのトラブルは未然に防ぐことができます。本記事では、中小企業の現場で本当に役立つユーザー権限管理の方法を、具体的な失敗例とその対策を交えながら解説します。
【要注意】中小企業でよく起こる5つの権限管理失敗パターン
まず最初に、私がこれまでのサポート業務で実際に遭遇した、中小企業でよく起こる権限管理の失敗パターンをご紹介します。これらの事例を知ることで、同様のトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
失敗例1:「とりあえず全員管理者」の落とし穴
「面倒だから、関係者全員に管理者権限を与えてしまえ」
これは中小企業で最もよく見られる失敗パターンです。ある美容室のオーナー様から緊急連絡をいただいたケースでは、アルバイトスタッフが「見た目を変えてみよう」と思って、WordPressのテーマを変更してしまいました。その結果、予約システムが動かなくなり、半日近くお客様の予約が取れない状態に陥ってしまったのです。
管理者権限を持つユーザーは、WordPressのすべての機能にアクセスできます。つまり、テーマの変更、プラグインの削除、重要な設定の変更など、サイト全体に影響を与える操作が可能になってしまうのです。
対策
各スタッフの業務に応じて、必要最小限の権限のみを付与することが重要です。記事の更新だけを担当するスタッフには「投稿者」権限、画像のアップロードや他の人の記事確認も行う場合は「編集者」権限というように、役割に応じた権限設定を行いましょう。
失敗例2:制作会社依存からの脱却失敗
「制作会社にすべて任せているから安心」と思っていませんか?
ある製造業の企業様では、急遽開催が決まった展示会の情報をサイトに掲載したいと制作会社に連絡したところ、担当者が休暇中で対応してもらえませんでした。管理者権限を制作会社のみが保有していたため、緊急性の高い情報発信ができず、貴重なビジネス機会を逃してしまったのです。
制作会社との適切な関係は重要ですが、自社でできることは自社で対応できる体制を整えておくことも同様に重要です。
対策
制作会社と協議の上、段階的に権限移譲を進めましょう。まずは記事投稿権限から始めて、慣れてきたら編集者権限、最終的には管理者権限の一部を自社で管理できる体制を構築することをお勧めします。ただし、これは十分な知識習得とサポート体制があることが前提となります。
失敗例3:退職者アカウントの放置リスク
人の入れ替わりが多い業界では特に注意が必要なのが、退職者のアカウント管理です。
ある小売店では、3年前に退職したスタッフのWordPressアカウントがそのまま残っていました。幸い実害はありませんでしたが、もしそのアカウントが何らかの理由で悪用された場合、サイトの改ざんや顧客情報の漏洩につながる可能性がありました。
退職者のアカウントが残ったままだと、パスワードが漏洩した場合やアカウントが乗っ取られた場合に、深刻なセキュリティインシデントに発展する恐れがあります。
対策
スタッフの入退社管理と連動したアカウント管理体制を構築しましょう。退職が決まった時点で、該当アカウントの削除または無効化を行う手順を明確にし、人事担当者とサイト管理者が連携する仕組みを作ることが重要です。
失敗例4:外部ライターへの権限付与ミス
コンテンツ制作を外部のライターに依頼する際の権限設定も、よくトラブルの原因となります。
ある士業事務所では、外部ライターに「投稿者」権限を付与していました。投稿者権限では記事の公開まで可能なため、チェック前の記事が公開されてしまい、専門的な内容に誤りがある記事がそのまま公開されてしまったのです。これにより、事務所の専門性に対する信頼を損なう結果となりました。
外部ライターとの協業では、記事の品質管理と公開タイミングの制御が重要になります。
対策
外部ライターには「寄稿者」権限を付与し、記事の作成・編集は可能だが公開はできない設定にしましょう。記事完成後は内部でチェックを行い、問題がないことを確認してから公開する承認フローを確立することが大切です。
失敗例5:「設定したら終わり」の継続管理不備
権限設定は一度行えば終わりではありません。業務内容の変更、組織改編、新システムの導入など、様々な要因で適切な権限設定は変化していきます。
ある建設会社では、営業担当だったスタッフが管理部門に異動したにも関わらず、営業情報にアクセスできる権限をそのまま保持していました。定期的な見直しを行っていなかったため、本来は見る必要のない情報にアクセスできる状態が続いていたのです。
対策
最低でも年2回、可能であれば四半期ごとに権限設定の見直しを行いましょう。各ユーザーの現在の業務内容と付与されている権限が適切かどうかをチェックし、必要に応じて権限の変更や削除を行う定期メンテナンスが重要です。
WordPressの5つのユーザー権限を理解しよう
失敗例を踏まえた上で、WordPressの基本的なユーザー権限について詳しく見ていきましょう。WordPressには、デフォルトで5つのユーザー権限が用意されており、それぞれ異なる機能にアクセスできるようになっています。
管理者(Administrator)
サイト全体の最高責任者
管理者はWordPressサイトのすべての機能にアクセスできる最高権限です。テーマの変更、プラグインのインストール・削除、ユーザーの追加・削除、サイトの各種設定変更など、サイト運営に関わるすべての操作が可能です。
中小企業では、サイト運営の最終責任者やIT担当責任者に付与するのが適切です。ただし、前述の失敗例のように、安易に多くの人に管理者権限を与えるべきではありません。
編集者(Editor)
コンテンツ全体の管理責任者
編集者は、投稿や固定ページに関するほぼすべての操作が可能です。自分が作成した記事だけでなく、他のユーザーが作成した記事の編集・削除・公開も行えます。また、コメントの管理やカテゴリーの設定なども可能です。
ただし、テーマやプラグインの変更、ユーザー管理、サイトの基本設定などはできません。社内でコンテンツ制作を統括する責任者や、複数のライターを管理するディレクターに適した権限です。
投稿者(Author)
自分の記事を完全管理
投稿者は、自分が作成した記事の作成・編集・公開・削除が可能です。メディアライブラリへのアクセスも可能なため、画像や動画のアップロードもできます。
しかし、他のユーザーが作成した記事は編集できません。社内で記事作成を担当するスタッフで、ある程度の自由度を持って記事公開まで行いたい場合に適しています。
寄稿者(Contributor)
記事作成専門
寄稿者は記事の作成・編集はできますが、公開はできません。記事完成後は編集者以上の権限を持つユーザーが内容を確認し、公開する仕組みになります。
外部ライターや、記事公開前に必ずチェック工程を経たい場合に適した権限です。ただし、メディアライブラリへのアクセスができないため、画像を含む記事の場合は運用方法を工夫する必要があります。
購読者(Subscriber)
閲覧専用
購読者は記事の閲覧のみが可能で、記事の作成・編集はできません。会員制サイトで一般会員に付与したり、記事公開前の内容確認のみを行う外部チェッカーに付与したりする際に使用します。
一般的な企業サイトではあまり使用する機会は少ないかもしれません。
権限別機能比較表
以下の表で、各権限でできることを整理しました。
| 機能 | 管理者 | 編集者 | 投稿者 | 寄稿者 | 購読者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 記事の閲覧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自分の記事作成・編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 自分の記事公開・削除 | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 他者の記事編集・公開 | ○ | ○ | – | – | – |
| メディアアップロード | ○ | ○ | ○ | – | – |
| コメント管理 | ○ | ○ | – | – | – |
| カテゴリー管理 | ○ | ○ | – | – | – |
| プラグイン管理 | ○ | – | – | – | – |
| テーマ管理 | ○ | – | – | – | – |
| ユーザー管理 | ○ | – | – | – | – |
| サイト設定変更 | ○ | – | – | – | – |
中小企業での推奨権限配分
業種や規模によって適切な権限配分は変わりますが、一般的な中小企業では以下のような配分をお勧めします。
管理者権限
サイト運営責任者1-2名まで。IT知識があり、サイト全体に責任を持てる人物に限定する。
編集者権限
マーケティング担当者やコンテンツ統括責任者。複数のスタッフが作成した記事をチェック・公開する役割の人。
投稿者権限
定期的に記事を作成し、ある程度自由に公開したい社内スタッフ。ただし、公開前チェックが不要なレベルの知識・経験を持つ人に限定。
寄稿者権限
外部ライター、新人スタッフ、記事作成は行うが公開判断は他の人に任せたい場合。
購読者権限
一般的な企業サイトでは使用機会は少ないが、会員制コンテンツがある場合などに使用。
【実践編】段階的権限管理導入のロードマップ
理論を理解したところで、実際にどのように権限管理を導入・改善していけばよいでしょうか。ここでは、段階的に取り組める実践的なロードマップをご紹介します。
- 現状把握と基本整理(1-2週間)
- まずは現在のWordPressサイトでどのようなユーザーアカウントが存在し、どのような権限が付与されているかを把握しましょう。
WordPressの管理画面から「ユーザー」→「ユーザー一覧」を確認し、以下の点をチェックしてください。
既存ユーザーの洗い出し
現在登録されているすべてのユーザーをリストアップし、それぞれの役割と現在の業務内容を確認しましょう。特に、すでに退職している人のアカウントが残っていないか、現在の業務内容と権限が適切かどうかを確認することが重要です。
権限の妥当性チェック
各ユーザーに付与されている権限が、現在の業務内容に適しているかを評価します。管理者権限を持つユーザーが多すぎる場合は、本当に管理者権限が必要かどうかを検討しましょう。
パスワード強度の確認
各アカウントのパスワードが十分に強固かどうかを確認します。古いパスワードのまま使い続けていたり、推測しやすいパスワードを使用していたりする場合は、この機会に変更を促しましょう。
- 基本的な権限再設定(2-3週間)
- 現状把握ができたら、適切な権限への再設定を行います。
不要なアカウントの削除
退職者や現在使用していないアカウントは削除します。ただし、そのユーザーが作成した記事や投稿がある場合は、事前に他のユーザーに投稿者を変更してから削除することを忘れずに行ってください。
権限の適正化
各ユーザーの現在の業務内容に応じて、適切な権限に変更します。管理者権限を持つユーザーを必要最小限に絞り、その他のユーザーは業務に応じて編集者、投稿者、寄稿者のいずれかに変更しましょう。
パスワードの強化
すべてのアカウントで強固なパスワードの設定を行います。12文字以上で、英大文字・小文字・数字・記号を組み合わせたパスワードを設定することをお勧めします。パスワード管理ツールの導入も併せて検討してください。
二段階認証の導入
管理者権限を持つアカウントについては、セキュリティプラグインを使用して二段階認証を設定することを強く推奨します。これにより、パスワードが漏洩した場合でも不正アクセスを防ぐことができます。
- 運用体制の構築(1ヶ月)
- 適切な権限設定ができたら、それを維持・管理する運用体制を構築します。
権限変更の申請フロー
新しいスタッフの入社や既存スタッフの業務変更があった場合の権限変更申請フローを明確にします。誰が申請し、誰が承認し、誰が実際の設定変更を行うかを決めておきましょう。
定期見直しスケジュール
最低でも年2回、理想的には四半期ごとに権限設定の見直しを行うスケジュールを設定します。この際、各ユーザーの現在の業務内容と権限が適切かどうかを確認し、必要に応じて変更を行います。
緊急時対応手順
アカウントの乗っ取りやサイトの改ざんなど、セキュリティインシデントが発生した場合の対応手順を明確にします。誰が初動対応を行い、どのような手順で復旧作業を進めるかを事前に決めておくことで、被害を最小限に抑えることができます。
文書化と共有
これらの運用ルールを文書化し、関係者全員が理解できるようにします。また、新しいスタッフが入社した際には、必ずこれらのルールについて説明する機会を設けましょう。
- 継続的な改善とモニタリング
- 権限管理は一度設定すれば終わりではありません。継続的な改善とモニタリングが重要です。
月次チェックポイント
毎月、新規ユーザーの追加状況、権限変更の実施状況、セキュリティインシデントの発生状況などを確認します。小さな変化でも記録しておくことで、問題の早期発見につながります。
年次大規模見直し
年に1回は、権限管理体制全体の見直しを行います。業務内容の変化、組織改編、新しいセキュリティ脅威の出現などを踏まえ、必要に応じて運用ルールの更新を行いましょう。
スタッフ教育の継続
権限管理の重要性やセキュリティ意識について、定期的にスタッフ教育を行います。新しい脅威や事例を共有し、全員のセキュリティ意識を高く保つことが重要です。
具体的なユーザー権限設定方法
ここからは、実際にWordPressでユーザー権限を設定する具体的な手順を説明します。まず、新しいユーザーを追加する方法から見ていきましょう。
新規ユーザーの追加手順
新しいスタッフや外部協力者をWordPressサイトに追加する場合の手順です。
WordPress管理画面にログインしたら、左側のメニューから「ユーザー」→「新規追加」をクリックします。新規ユーザー追加画面が表示されますので、以下の項目を入力してください。
ユーザー名
ログイン時に使用するIDです。半角英数字で設定し、推測されにくいものにしましょう。本名をそのまま使用するのは避け、本名に数字を組み合わせるなどの工夫をお勧めします。
メールアドレス
ユーザーが普段使用しているメールアドレスを設定します。パスワードリセット時などに使用されるため、確実に受信できるアドレスを設定してください。
名・姓
実際の氏名を入力します。これは記事の投稿者名として表示される場合があります。
パスワード
強固なパスワードを設定します。WordPressが自動生成するパスワードを使用するか、12文字以上で英大文字・小文字・数字・記号を組み合わせたパスワードを設定してください。
権限グループ
最も重要な設定です。そのユーザーの業務内容に応じて、適切な権限を選択してください。迷った場合は、より制限の厳しい権限から始めて、必要に応じて後から権限を拡大することをお勧めします。
ユーザーに通知を送信
チェックを入れると、設定したメールアドレスにログイン情報が送信されます。通常はチェックを入れておきましょう。
すべての項目を入力したら「新規ユーザーを追加」ボタンをクリックして完了です。
既存ユーザーの権限変更手順
すでに登録されているユーザーの権限を変更したい場合の手順です。
WordPress管理画面の左側メニューから「ユーザー」→「ユーザー一覧」をクリックします。登録されているユーザーの一覧が表示されますので、権限を変更したいユーザーの行にマウスを合わせ、「編集」をクリックしてください。
ユーザー編集画面が表示されたら、「権限グループ」の項目を確認してください。現在設定されている権限が表示されていますので、プルダウンメニューから新しい権限を選択します。
その他にも、この画面では以下の設定を変更できます。
プロフィール情報の更新:
連絡先情報や自己紹介文などを追加・変更できます。
パスワードの変更
新しいパスワードを設定できます。定期的なパスワード変更を推奨している場合は、この機能を活用してください。
表示名の設定
記事投稿時に表示される名前を設定できます。本名以外のペンネームなどを使用したい場合に活用してください。
設定変更が完了したら、画面下部の「ユーザーを更新」ボタンをクリックして保存してください。
権限設定時の注意点
権限設定を行う際に注意すべきポイントをいくつかご紹介します。
段階的な権限付与
新しいユーザーには、最初は制限の厳しい権限から始めて、慣れてきたら徐々に権限を拡大することをお勧めします。いきなり高い権限を与えてしまうと、誤操作のリスクが高まります。
権限変更の記録
誰がいつどのような権限変更を行ったかを記録しておきましょう。問題が発生した際の原因究明や、定期見直し時の参考情報として活用できます。
テスト環境での事前確認
重要な権限変更を行う前に、可能であればテスト環境で動作確認を行うことをお勧めします。本番環境での予期しない動作を防ぐことができます。
バックアップの取得
権限変更を行う前には、必ずサイト全体のバックアップを取得しておきましょう。万が一問題が発生した場合でも、すぐに元の状態に戻すことができます。
プラグインを活用した高度な権限管理も
WordPressの標準機能だけでは対応できない、より細かな権限設定が必要な場合があります。そのような場合は、専用のプラグインを活用することで、より柔軟な権限管理が可能になります。
User Role Editorプラグインの活用
「User Role Editor」は、WordPressの権限設定をより細かくカスタマイズできる無料プラグインです。このプラグインを使用することで、既存の権限グループの権限を変更したり、新しい権限グループを作成したりすることができます。

プラグインをインストールして有効化すると、WordPress管理画面の「ユーザー」メニューに「User Role Editor」という項目が追加されます。これをクリックすると、権限設定画面が表示されます。
この画面では、各権限グループが持っている個別の権限を確認・変更できます。例えば、「寄稿者」権限にメディアアップロード機能を追加したり、「投稿者」権限から投稿公開機能を削除したりすることが可能です。
中小企業に適したカスタム権限設定例
実際の業務に合わせたカスタム権限の設定例をいくつかご紹介します。
画像投稿可能な寄稿者権限
外部ライターに画像付きの記事を作成してもらいたい場合、標準の寄稿者権限にメディアアップロード機能を追加します。これにより、記事作成時に画像をアップロードできるようになりますが、記事の公開は依然として制限されたままです。
限定的な編集者権限
コンテンツ管理は任せたいが、サイトの基本設定は触ってほしくない場合、編集者権限から一部の機能を削除することができます。例えば、プラグインの設定変更やテーマカスタマイザーへのアクセスを制限することで、より安全な運用が可能になります。
部門別権限の設定
大きめの中小企業で部門ごとに担当するコンテンツが異なる場合、部門別の専用権限を作成することもできます。営業部は営業関連のカテゴリーのみ編集可能、技術部は技術情報のみ編集可能といった設定が可能です。
プラグイン導入時の注意点
権限管理プラグインを導入する際には、いくつかの注意点があります。
事前テストの実施
本番環境に導入する前に、必ずテスト環境で十分なテストを行ってください。権限設定の変更は、サイトの動作に大きな影響を与える可能性があります。
バックアップの取得
プラグインの設定変更前には、必ずサイト全体のバックアップを取得してください。設定ミスがあった場合でも、すぐに元の状態に戻すことができます。
設定内容の文書化
カスタムした権限設定の内容は、必ず文書として記録しておきましょう。設定理由や変更履歴も併せて記録することで、後任者への引き継ぎがスムーズになります。
定期的な見直し
カスタム権限も、定期的に見直しを行うことが重要です。業務内容の変化や新しいセキュリティ要件に応じて、適切に調整していきましょう。
業種別権限設定のベストプラクティス
業種や業態によって、適切なユーザー権限の設定は変わってきます。ここでは、代表的な業種での一例ですが、権限設定のベストプラクティスをご紹介します。
飲食店・美容室などの店舗系ビジネス

店舗系のビジネスでは、スタッフの入れ替わりが多いことが特徴です。そのため、アカウント管理の簡素化と、セキュリティの両立が重要になります。
オーナー・店長
管理者権限を付与し、サイト全体の管理を行います。ただし、複数店舗を展開している場合は、各店舗の店長には編集者権限に留め、本部のWeb担当者のみが管理者権限を持つ構成も検討してください。
正社員スタッフ
定期的にブログ更新やお知らせ投稿を行う正社員には、投稿者権限を付与します。ただし、新人スタッフの場合は最初は寄稿者権限から始めて、慣れてきたら投稿者権限に昇格させることをお勧めします。
アルバイト・パートスタッフ
基本的には権限を付与せず、必要に応じて正社員が代理投稿する体制をお勧めします。どうしても直接投稿してもらいたい場合は、寄稿者権限に留めて、必ず承認プロセスを経るようにしてください。
外部業者(清掃業者、設備保守など)
一般的には権限付与は不要ですが、定期的な作業報告をサイトに掲載したい場合は、寄稿者権限を付与し、承認後に公開する運用を行ってください。
店舗系ビジネスでは、特に退職者アカウントの削除を迅速に行うことが重要です。退職が決まった時点で、すぐにアカウントを無効化または削除する手順を確立しておきましょう。
士業・コンサルティングなどの専門サービス業

専門サービス業では、専門性の高い情報を扱うため、コンテンツの品質管理と機密情報の保護が重要になります。
代表・パートナー: 管理者権限を付与しますが、日常的な記事投稿では編集者権限のアカウントを別途作成して使用することをお勧めします。管理者権限は重要な設定変更時のみ使用する運用が理想的です。
シニアコンサルタント・上級スタッフ: 編集者権限を付与し、専門記事の作成・公開を行います。ただし、法的な問題に関わる内容については、必ず代表またはパートナーのチェックを経る社内ルールを設けることをお勧めします。
ジュニアスタッフ: 寄稿者権限から始めて、経験を積んだら投稿者権限、さらに経験を積んだら編集者権限へと段階的に昇格させる仕組みを作ってください。
外部ライター: 専門分野に精通した外部ライターを活用する場合でも、必ず寄稿者権限に留め、内部でのチェック・承認プロセスを経てから公開してください。
専門サービス業では、記事内容の正確性が事業の信頼性に直結するため、承認プロセスを軽視しないことが重要です。
製造業・建設業などのBtoB企業

BtoB企業では、技術情報や企業機密に関わる情報を扱うことが多いため、情報の取り扱いレベルに応じた権限管理が必要になります。
経営陣・事業部長
管理者権限を付与しますが、技術的な操作は専任担当者に委託し、経営判断に関わる重要な変更時のみ使用する運用をお勧めします。
マーケティング・広報担当
編集者権限を付与し、企業情報、製品情報、ニュースリリースなどの投稿・管理を行います。技術的な詳細については、技術部門との連携を取る体制を構築してください。
技術部門スタッフ
技術情報の投稿を行う場合は、投稿者権限または寄稿者権限を付与します。機密度の高い技術情報については、必ず上司の承認を経てから公開する運用を徹底してください。
営業スタッフ
顧客事例や導入実績などを投稿する場合、寄稿者権限を付与し、マーケティング部門での承認を経てから公開する体制をお勧めします。
BtoB企業では、競合他社に知られたくない情報や、顧客との機密保持に関わる情報の取り扱いに特に注意が必要です。
小売・ECなどの販売業

販売業では、商品情報の更新頻度が高く、価格情報などの正確性が重要になります。また、在庫情報との連動も考慮する必要があります。
店舗責任者・EC責任者
管理者権限を付与し、サイト全体の管理を行います。ただし、価格変更などの重要な変更については、必ず複数人でのチェック体制を構築してください。
商品企画・マーチャンダイザー
編集者権限を付与し、商品情報、特集記事、キャンペーン情報などの管理を行います。
販売スタッフ
店舗ブログやスタッフ紹介、商品レビューなどを投稿する場合、投稿者権限を付与します。ただし、価格情報や在庫情報に関わる投稿は避け、そうした情報が含まれる場合は編集者の承認を必要とする運用をお勧めします。
倉庫・物流スタッフ
基本的には権限付与は不要ですが、商品の入荷情報や配送状況などを投稿する場合は、寄稿者権限を付与し、必ず販売部門での承認を経る体制を構築してください。
販売業では、特に価格情報の誤りが直接的な損失につながる可能性があるため、価格に関わる情報の投稿・変更には十分な注意が必要です。
法的観点から見たユーザー権限管理
ユーザー権限の管理は、単なるシステムの運用上の問題ではなく、法的な観点からも重要な意味を持ちます。特に個人情報保護法との関係では、適切な権限管理が法的要件となる場合があります。
個人情報保護法との関係
2022年4月に施行された改正個人情報保護法では、個人情報の適切な管理がより厳格に求められるようになりました。WordPressサイトで顧客情報や問い合わせ情報を扱う場合、以下の点に注意が必要です。
アクセス制限の実施
個人情報にアクセスできる人を、業務上必要な最小限の人員に限定する必要があります。WordPressの権限設定により、個人情報を含む投稿やページへのアクセスを適切に制限してください。
アクセスログの記録
誰がいつ個人情報にアクセスしたかを記録し、定期的に監査を行う体制を構築する必要があります。権限変更の履歴も含めて、適切に記録・保管してください。
データの最小化
不要な個人情報の収集・保管を避け、必要最小限のデータのみを扱うようにしてください。古い問い合わせ情報などは、法定保存期間を過ぎたら適切に削除しましょう。
必要な記録の保管方法
法的要件を満たすために、以下の記録を適切に保管することをお勧めします。
ユーザーアカウント管理台帳
現在登録されているすべてのユーザーアカウント、その権限、最終ログイン日時などを記録した台帳を作成し、定期的に更新してください。
権限変更履歴
いつ、誰が、どのような権限変更を行ったかの履歴を記録してください。変更理由も併せて記録することで、監査時の説明が容易になります。
セキュリティインシデント対応記録
不正アクセスや情報漏洩などのインシデントが発生した場合の対応記録を保管してください。今後の予防策検討にも活用できます。
研修・教育実施記録
スタッフに対するセキュリティ教育の実施記録も重要な証拠書類となります。いつ、誰に、どのような内容の教育を行ったかを記録してください。
監査対応のポイント
個人情報保護委員会などからの監査要求があった場合に備えて、以下の点を準備しておくことをお勧めします。
体制図の整備
個人情報の管理体制を図で示し、各担当者の役割と権限を明確にしてください。WordPressのユーザー権限設定も、この体制図と整合性を取る必要があります。
規程・マニュアルの整備
個人情報の取り扱いに関する社内規程やマニュアルを整備し、実際の運用と整合性を取ってください。
技術的安全管理措置の実施
アクセス制御、外部からの不正アクセス防止、情報漏洩防止などの技術的な対策を実施し、その内容を文書化してください。
定期的な見直し・改善
個人情報保護の取り組みは一度実施すれば終わりではなく、継続的な改善が求められます。定期的に見直しを行い、その記録を保管してください。
まとめ:データドリブンな権限管理で安全なサイト運営を
WordPressのユーザー権限設定と管理は、中小企業のサイト運営において極めて重要な要素です。本記事でご紹介した失敗例を参考に、同様のトラブルを未然に防いでいただければと思います。
重要なポイントを改めて整理すると、まず「最小権限の原則」を徹底することです。各ユーザーには、その業務に必要な最小限の権限のみを付与し、不要な権限は与えないことが基本となります。
次に、継続的な管理体制の構築です。権限設定は一度行えば終わりではなく、組織の変化や業務内容の変更に応じて、継続的に見直しを行う必要があります。
また、法的要件への対応も忘れてはいけません。個人情報保護法をはじめとする各種法令への適切な対応は、企業の信頼性に直結する重要な課題です。
データドリブンなアプローチとして、IPAの実態調査にもあるように、セキュリティ対策を実施している企業ほど、実際のインシデント発生率が低下しています。つまり、適切な権限管理は確実にリスクを軽減する効果があるのです。
私たち「戦略的ウェブ制作工房 エル・タジェール」では、中小企業の皆様が安全で効果的なWordPressサイト運営を行えるよう、権限管理を含む総合的なサポートを提供しています。「作って終わり」ではなく、お客様のビジネス成長を継続的に支援するパートナーとして、権限管理の導入から運用まで、きめ細かくサポートいたします。
WordPressのユーザー権限管理でお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の業種・規模・運営体制に最適な権限管理体制の構築をお手伝いいたします。
適切なユーザー権限の設定と管理により、安全で効率的なWordPressサイト運営を実現し、ビジネスの成長を加速させていきましょう。